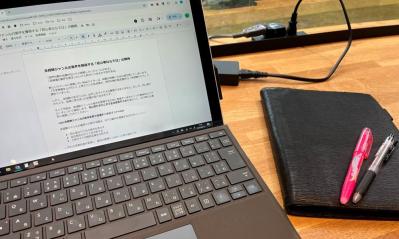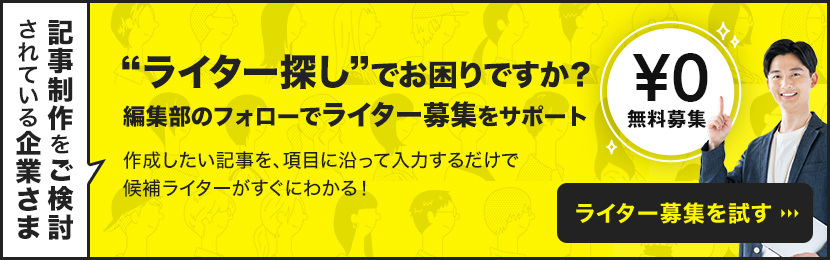知らないジャンルでも記事を書ける理由

「全く知らないジャンルの記事を書けるの?」と不安になることはありませんか? 実は、専門知識がなくても、適切なリサーチをすれば全く知らないジャンルでも記事を書けます。
ここでは、ライターが未経験ジャンルでも執筆できる理由を解説します。
ライターに必要なのは「専門知識」ではなく「情報整理能力」
ライターは必ずしも専門家である必要はありません。
大切なのは、膨大な情報をリサーチ・整理し、読者にとってわかりやすい形で伝える能力です。
つまり、適切なリサーチスキルと文章構成力があれば「知らないジャンルの記事」を書けるようになります。
「知らないこと」はリサーチで解決できる
知識がゼロの分野でも、リサーチを徹底すれば、読者に役立つ専門性のある記事を書けます。Google検索で上位の記事を分析し、どのような情報が求められているのかを把握しましょう。
信頼できる情報源を優先的に調査し、正確な知識を取得することも大切です。リサーチで得た情報を整理し、わかりやすく伝えることで、未経験のジャンルでも質の高い記事を作成することが可能になります。
読者視点を持つ
ライターは専門家ではなく、読者の疑問を解決するために情報を集め、わかりやすく伝える役割を担っています。読者と同じ目線で「どんな情報が必要か」「どうすれば理解しやすいか」を常に意識してください。
専門的な内容であっても、初心者でも理解できるように、具体例やシンプルな言葉を使って説明すると効果的です。読者の立場に立ち「自分が知りたいと思う記事」を書くことで、満足度の高いコンテンツになるでしょう。
【筆者の体験談】
とあるクライアントから「探偵(浮気調査)」に関する記事執筆を依頼された経験があります。探偵にはこれまでの人生でお世話になったことがなく、全く知らない世界でした。
しかし、徹底的にリサーチして執筆した結果、無事に執筆が完了し、納品できました。大切なのは「読者の視点で、読者の身になって執筆」することです。
関連記事
ゼロから始めるリサーチの進め方

知らないジャンルの記事を書くには、リサーチが欠かせません。情報を集め、整理し、読者が求める形にすることで説得力のある記事になります。
ここでは、知らないジャンルを執筆するのに効果的なリサーチの方法を詳しく解説します。
①クライアントの要望を正しく把握する
最初に、クライアントの意図を明確にしましょう。クライアントの要望を正しく把握することで、記事の目的やターゲットが明確になり、求められる内容に沿った質の高い記事を作成できます。
- 記事の目的の設定(SEO対策/集客/商品PRなど)
読者が求める情報を的確に提供でき、知りたいことをスムーズに解決できる - 想定読者の設定(初心者向け/専門家向けなど)
読者に合った内容やレベルで書かれるため、理解しやすく、満足度が高まる - 記事のゴールを設定(CTA)
読者が次に取るべき行動が分かりやすくなり、迷わず行動できる
②シークレットモードで上位記事を分析する
Google検索でリサーチをする際には、検索履歴や個人の興味などの閲覧履歴に影響されないよう、シークレットモードを活用して検索します。
シークレットモードとは、Google Chromeアプリに搭載されている検索履歴や閲覧履歴を残さずにインターネットを利用できるブラウザの機能です。客観的な検索結果を得られるため、正確なリサーチができます。
シークレットモードで検索した上位20記事の内容を確認し、下記の項目をリストアップしましょう。
- よく使われているキーワード
- 記事の構成(どの順番で説明されているか)
- 読者の疑問点を解決できる情報があるか
③サジェストキーワードで深掘りする
サジェストキーワードとは、検索エンジンにキーワードを入力した際に、自動的に表示される関連語や予測ワードです。
Googleの検索窓にキーワードを入力すると、サジェストキーワードが表示されます。
「Googleキーワードプランナー」や「ラッコキーワード」「Ubersuggest」などのツールを活用するのも有効です。
サジェストキーワードを活用することで、読者が実際に検索する関連ワードを洗い出し、よりニーズに合う記事を執筆できます。
【筆者が使用しているツール】
筆者が使っているのは「ラッコキーワード」です。課金して使用しています。
サジェストキーワードのほか、見出しの抽出、共起語の表示など多彩な機能で便利です。
④信頼できる情報源を見極める
「◯◯知恵袋」や「教えて◯◯」のような投稿型Q&Aサイト系の情報の中には、信頼性の低い情報があります。信頼性の低い情報をもとに執筆すると記事の質が下がるだけでなく、クライアントや読者からの信頼も失いかねません。
リサーチする際は、以下の情報源を優先しましょう。
- 政府機関・公的機関のサイト(.gov, .go.jp)
- 大学・研究機関の論文(Google Scholarなど)
- 業界団体・企業の公式サイト
- 専門家による解説記事
上記のサイトは、公的機関や専門家によって管理・運営され、信頼性の高いデータや専門的な情報が提供されているため、正確性と権威性が保証されているといえます。
【筆者の場合】
シークレットモードで検索し、上位20位以内であっても、信頼できないサイトと判断した記事は参考にしません。たとえ下位であっても、上記に挙げたような信頼できるサイトを参照しています。
⑤競合記事との差別化ポイントを見つける
リサーチした内容をそのまま書くだけでは、ありふれた記事になってしまいます。
差別化するためには、競合記事をよく分析し「書かれていない視点」や「よりわかりやすく説明できる方法」を考えましょう。
【筆者が実行している差別化】
経験したことのあるキーワードであれば「筆者の体験・経験」を盛り込むようにしています。執筆者の「体験・経験」は、Googleが重視している項目です。
「体験・経験」が記載され、有益性が高いとGoogleに判断されたら、検索上位に表示される確率が高くなります。
関連記事
知らないジャンルでも読者に伝わる執筆のコツ

「知らないジャンルの記事は難しい」と思うかもしれませんが、実は初心者だからこそわかりやすく書く視点を持てます。筆者が「探偵(浮気調査)」の記事を執筆した際も、専門知識がないからこそ読者に寄り添った記事を書けました。
ここからは、筆者の体験を例に挙げながら「知らないジャンルでも読者に伝わる執筆のコツ」を解説していきます。
① 難しい専門用語を使わず、わかりやすく言い換える
例えば「内偵調査」などの業界用語は、読者に伝わりにくいので「バレずに情報を集める調査」と言い換えました。専門知識がないからこそ、初心者でも理解できる表現を意識できます。
② 「自分の疑問」を読者の疑問として反映する
「探偵ってどんなことをするの?」「調査の流れは?」など、自分が気になったことをそのまま記事の見出しにしました。初心者の疑問を解決することで、読者に寄り添った記事になります。
③ 具体例を入れてイメージしやすくする
「Aさん(30代女性)が夫の行動を怪しみ探偵に依頼。無料相談→尾行調査→証拠報告書の流れで進む」など、実際のケースを想定すると、読者がより理解しやすくなります。
④ 読み手の立場で文章を見直す
専門家ではないからこそ「この説明で、読者に本当に伝わるのか?」と思えます。わかりにくい部分を削り、シンプルに仕上げました。
初心者だからこそ「読者の疑問」を深掘りし、わかりやすい記事を書けます。業界用語を避け、疑問を解決し、具体例を入れる。この工夫を意識すれば、知らないジャンルでも伝わる記事を書けるでしょう。
知らないジャンルだからこそ、読者目線になれる
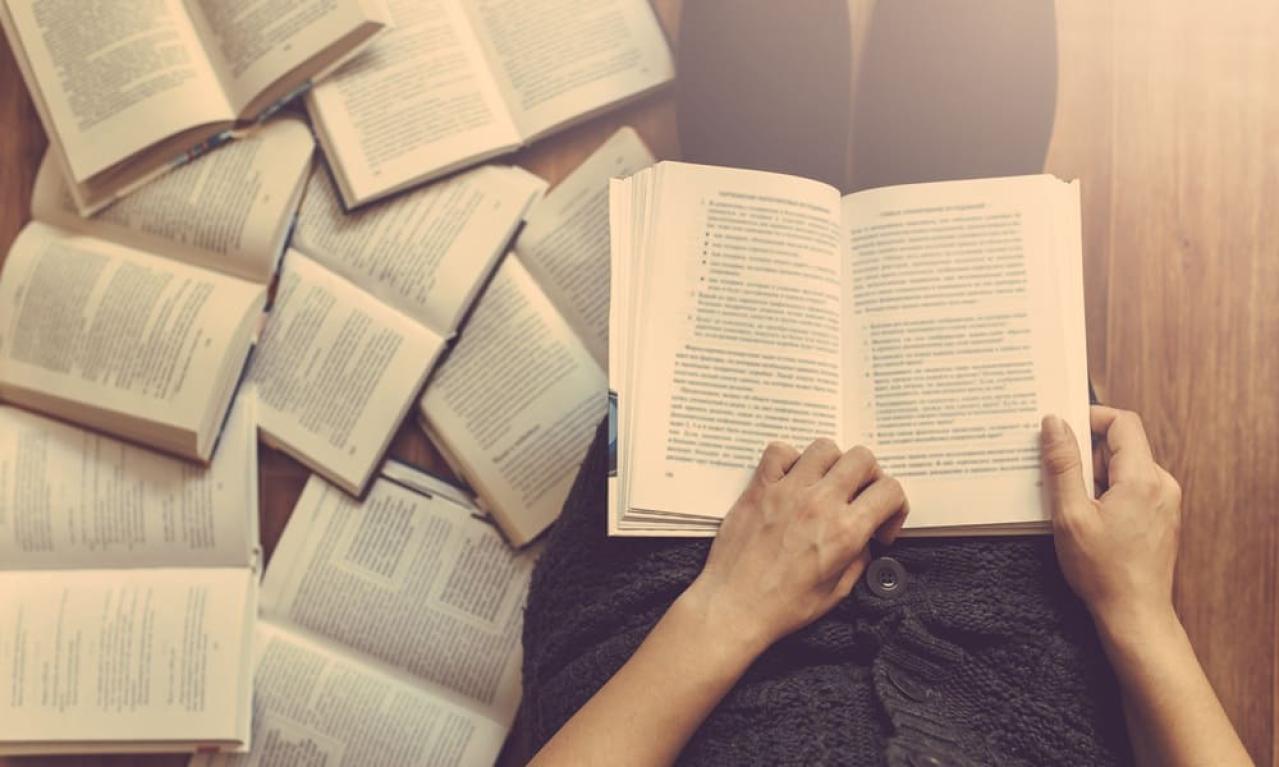
未経験のジャンルでも、適切なリサーチと伝わる文章の書き方を意識すれば質の高い記事を執筆できます。キモは「検索上位記事の徹底的なリサーチ」です。ライターとしてのスキルを磨きながら、どんなジャンルでも対応できる力をつけていきましょう。
ただし、忘れてはならないのは「クライアントファースト」と「読者ファースト」です。クライアントの要望に応え、読者の悩みを解決できる記事に仕上げてください。
筆者は、この記事で解説している内容を心がけて執筆するようになってから、クライアントからの執筆継続依頼が増えました。継続案件をゲットしてライターとしての成功を目指しましょう!
この記事が、ライターの皆さまのお役に立てば幸いです。皆さまの活動を応援しています。
この記事を書いたライター
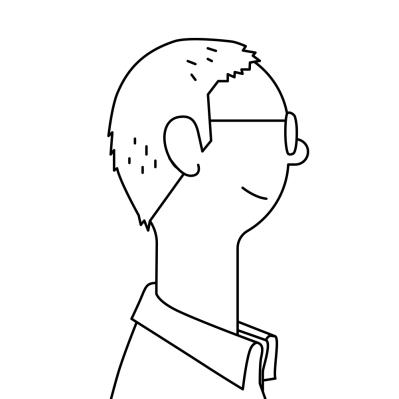
緒方智幸
モットーは「読者ファースト」。昭和40年(1965年)生まれ、孫がいるおじいちゃんライターです。趣味はオートバイ。1984年から乗ってます。最近のマイブームはバイクで行く神社巡りと御朱印集めです。Webライターデビューは、57歳のとき。「50代...