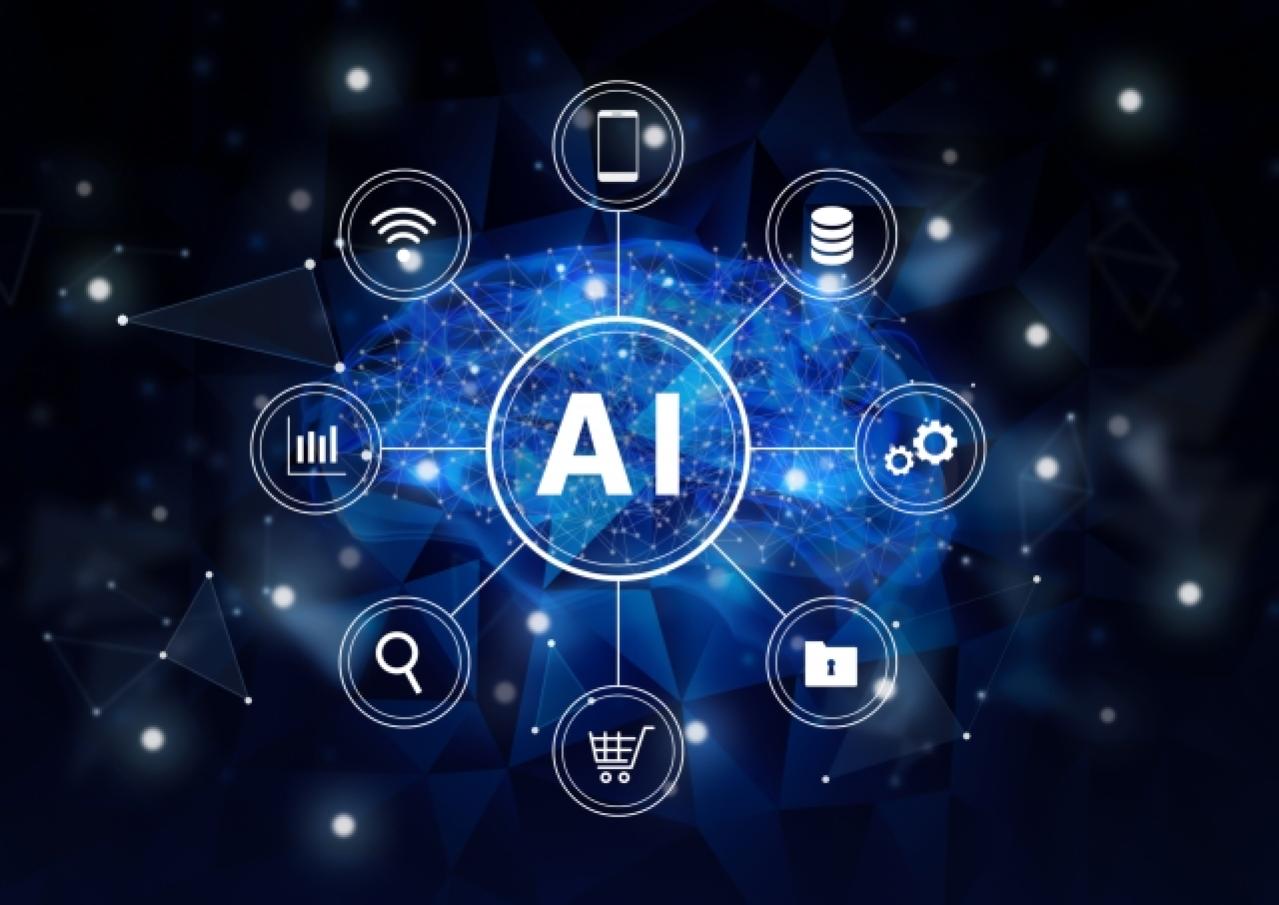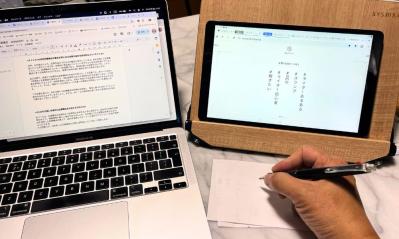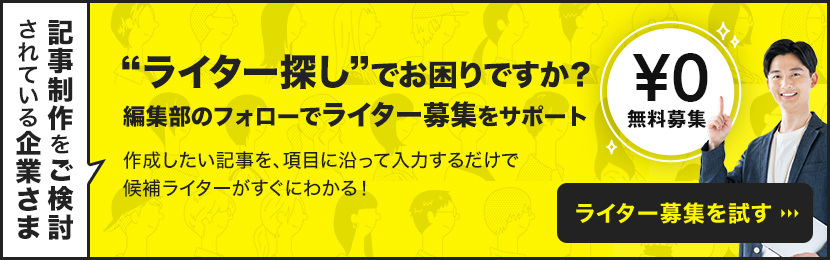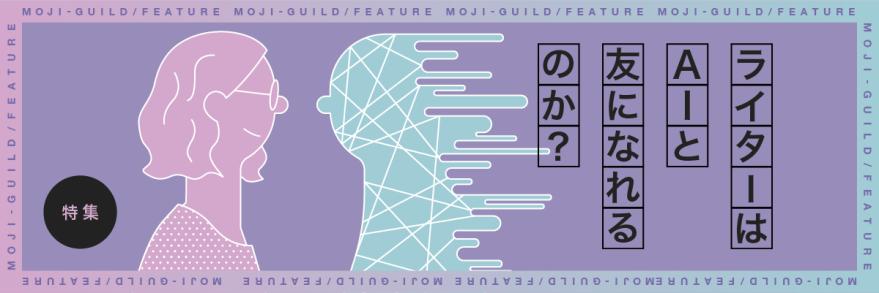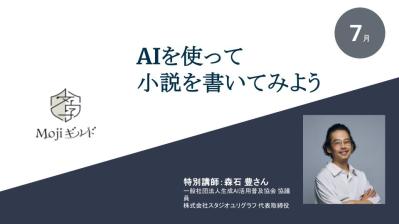ライターの仕事でAIツールが構成や執筆以外で活用できるシーン

ライターの仕事と聞くと「構成を考えて記事を書く」ことが中心だと思われがちですが、実際には執筆以外のタスクも多く存在します。
クライアントとのメールはもちろん、仕事獲得を目的としたSNSの発信、資料作成など、周辺業務に多くの時間を取られるケースも少なくありません。
ここからは、構成や執筆以外で私が実際にライターの仕事でAIツールを活用しているシーンを以下5つに厳選して紹介します。
- 記事の評価
- メール対応
- SNS運用
- ホワイトペーパー作成
- 研修資料作成
上記のようなシーンでAIツールを活用できれば、時間短縮や品質向上につながります。
記事の評価
自分の文章を客観的に評価するのは意外と難しいものですが、AIを活用して記事のレビューをもらう方法があります。
クライアントワークで提出先の企業に編集者やディレクター(チェッカー)がいれば、執筆を終えた記事の添削をしてもらえます。
しかし、実際のクライアントワークでは「添削してもらうための記事」を提出すると、継続につながらない可能性もあるのです。
AIに文章を読み込ませると、プロンプト次第で以下の要素におけるフィードバックを得られます。
- 冗長な部分がないか
- 語尾のバリエーションは十分か
- SEO的に不足しているキーワードは何か など
最終的には人間の判断が必要ですが、AIを「第2のチェック担当」として活用することで、より質の高い記事を仕上げられるでしょう。
メール対応
AIツールを使えば、丁寧でビジネスライクな文章を短時間で生成できます。
ライターとして仕事を進めるうえで、クライアントとのやり取りは欠かせません。依頼内容の確認や納期調整、修正依頼への返答など、メール対応に意外と時間がかかるものです。
「修正点を承知しました。対応後、再度ご連絡いたします」といった基本的な返信文をテンプレートとして残しておくと、文章入力の時間が短縮できます。
また、以下のシーンでクライアントからメールがあった際の回答文をテンプレート化する活用方法もあります。
- 追加費用が発生する場合の説明文
- 納期延長を依頼する際の丁寧な交渉文 など
AIに下書きを作らせて自分で最終調整すれば、時間を節約しつつ失礼のないやり取りができるのです。
SNS運用
ライターとしてSNSを活用し、アカウントをポートフォリオ代わりに使う際もAIツールがおすすめです。
ライター自身がSNSで情報発信し、クライアントからのオファーや応募活動をするためにアカウントを開設している方もいるでしょう。
しかし、毎日継続的に発信するのは「何を投稿しよう……」と悩む方も多いため、つい更新が止まってしまうものです。
SNS運用でAIツールを活用すれば、記事公開のお知らせ文を短くキャッチーにまとめたり、投稿ネタをブレストしたりするのに活用できます。
自分の強みをAIに理解させれば、自然な文章での発信を継続しやすくなり、「この人に依頼したい」と思ってもらえるきっかけになるでしょう。
ホワイトペーパー作成
企業案件に携わるライターの場合、記事執筆だけでなく「ホワイトペーパー」の作成を任される仕事もあります。ホワイトペーパーは、潜在顧客に提供するPDF資料で、専門的かつ信頼性の高い情報が求められます。
AIは文章の下書きだけでなく、資料の構成案作成や見出し候補の提示、専門用語の解説文生成などに役立つため、制作時間の短縮が可能です。
また、データをわかりやすく要約したり、図表に変換したりする際のサポートにもAIツールを活用できます。
資料作成代行は通常、サービスの特徴を理解してから始まるため、相当な時間を要しますが、AIを活用すると効率的に完成度の高い資料が仕上がります。
研修資料作成
ライターとして活動していると、場合によっては「新人教育用のマニュアル」や「研修の資料」を作る機会も出てきます。
研修資料はわかりやすさと体系性が重視されるため、ゼロから作るのは負担が大きいものです。
AIを使えば、研修内容に合わせてスライド構成案を出したり、専門用語を平易に説明する文章を生成したりできます。
さらに、実際のケーススタディやクイズ形式の問題も、AIに考えてもらえるため悩む時間が短縮されます。
単なる読み物ではなく「参加者の理解を深める」資料を短時間で整えられると、ライターとしての付加価値も高まるのです。
ライターの仕事でAIツールを使用する際の注意点
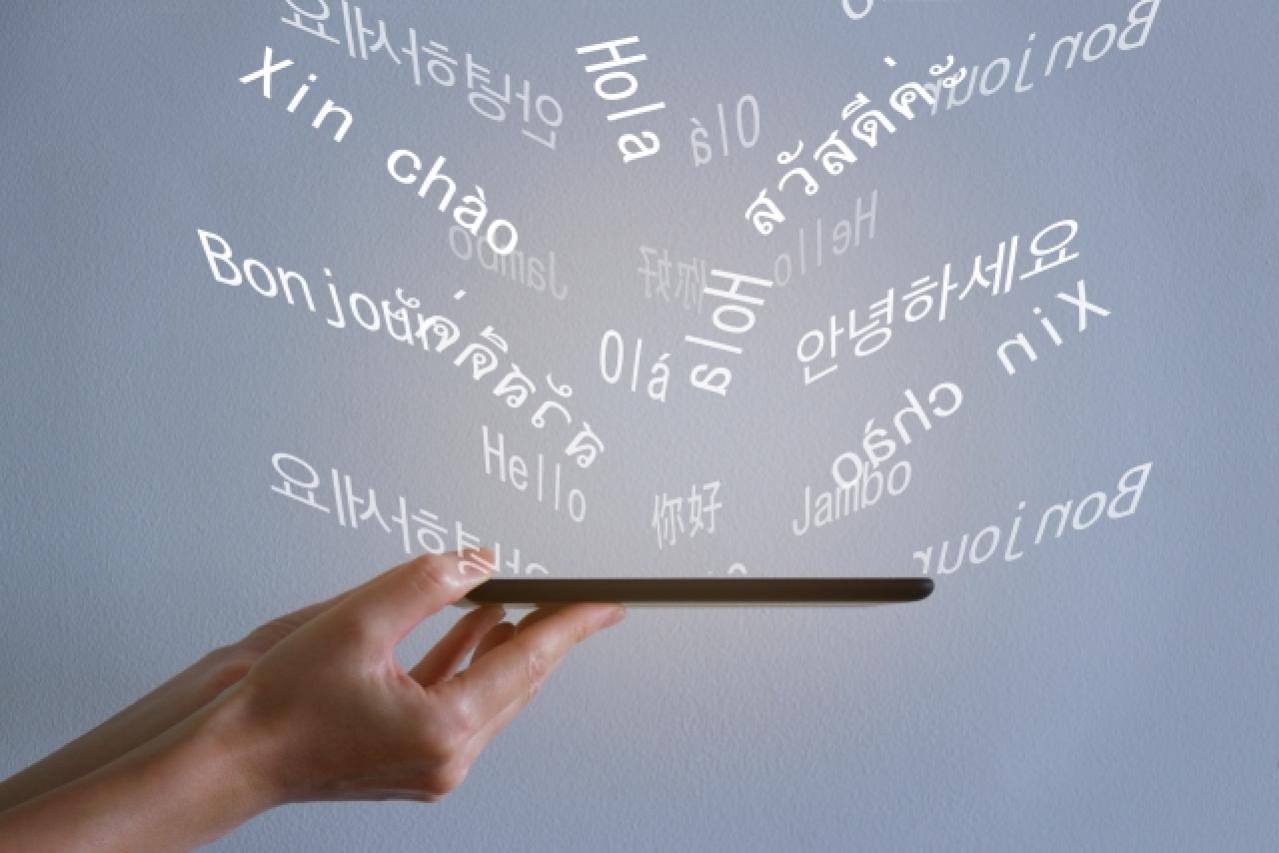
AIは便利な一方で、使い方を誤るとトラブルの原因になります。
特にライターの仕事は、クライアントの信頼を背負って仕事をする立場であるため、リスクを理解したうえで活用しなければいけません。
ここからは、AIツールの活用にあたって注意すべき3つのポイントを解説します。
- 個人情報の漏洩
- 誤情報の生成
- 倫理観の欠如
個人情報の漏洩
AIにクライアント名や案件内容などの情報を入力する際には、必ず情報管理に注意しましょう。
多くのAIツールは入力内容を学習や保存に利用する可能性があり、無防備に書き込むと情報漏洩につながるリスクがあります。
特に未公開の企画内容や社外秘の情報、個人情報などをそのまま入力するのは厳禁です。
利用する際はプライバシーポリシーを確認し、必要に応じて匿名化や伏字処理を行いましょう。
誤情報の生成
AIは自然な文章を生み出しますが、必ずしも正しい情報を提供してくれるわけではありません。
事実確認をせずにAIが出した文章をそのまま使うと、誤った情報を拡散してしまい、信頼を損なう可能性があります。
ライターとしては、AIの出力をあくまで「叩き台」として利用し、自分の手で裏取りや情報精査(ファクトチェック)することが必須です。
特に専門性の高いジャンルでは、チェックを怠ると致命的なミスにつながってしまいます。なお、本記事で解説した内容を、クライアントによっては「ハルシネーション」と呼ぶケースもあります。
参考:Google Cloud「AI ハルシネーションとは」
倫理観の欠如
AIが生成する文章は便利ですが、倫理的な配慮が欠けている場合もあります。
差別的な表現や偏った視点を含んだ文章をそのまま利用すると、クライアントや読者に不快感を与えてしまいます。
たとえばAIで生成した文章をそのまま拡散力のあるXで投稿した際、差別表現があると炎上につながるリスクがあるのです。
ライターは常に「AIは補助的なツール」という意識を持ち、最終的な責任は自分にあると認識して活用する意識が大切です。
まとめ:AIを「扱う」ライターになろう!

AIは構成や執筆だけでなく、記事のレビュー、メール対応、SNS運用、資料の作成など、多方面でライターの仕事をサポートしてくれます。
しかし、個人情報の管理や誤情報の精査、倫理観などの注意点を無視すると、便利さが一転して、リスクへと変わってしまいます。
「AIに任せきり」ではなく「AIを扱えるライター」になることが大切です。
補助ツールとしてAIを賢く取り入れると、時間を効率的に使いながら成果物の質を高められます。
副業でライターを始めようと思っている方、始めたばかりの方にとっても、AIを扱うスタンスを持つことが、差別化や信頼獲得につながります。
この記事を書いたライター

柴﨑 祐介
専業SEOライター|僧侶→営業→コールセンターの異業種から2023年専業Webライターとして独立|電子書籍出版の経験をもとにSNSマーケティングや転職をはじめ、ジャンル問わず多数執筆|AIツールを活用しつつ「AIに負けない×届けたい本質を形に!」...