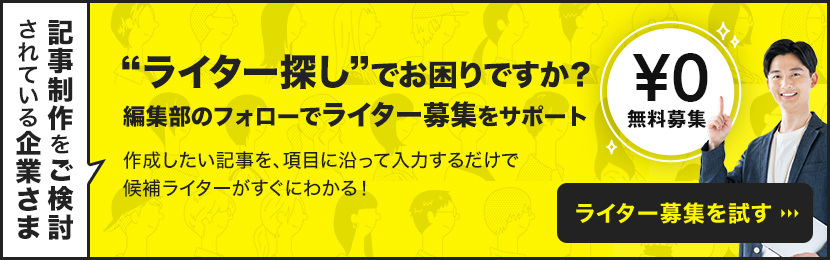そもそも“好き”と“得意”はどう違うのか?

「好きなジャンルで書けば、自然と筆が進む」
そんなふうに思われがちですが、実際にはそう単純な話ではありません。
「好き」なのに筆が進まないこともあれば、「得意」なのにまったく気乗りしないこともある。むしろ、このふたつが混ざり合って見えにくくなっているからこそ、多くのライターがジャンル選びで迷い、壁にぶつかるのかもしれません。
この章ではまず、「好き」と「得意」の違いを整理したうえで、なぜ「好き」なのに疲れてしまうのか、その背景を掘り下げていきます。
「好き」は感情、「得意」はスキル
「好き」と「得意」は、しばしば混同されがちですが、実はまったく異なる性質を持っています。
「好き」とは、言い換えれば“気持ち”です。興味があったり、ジャンルに触れているだけで楽しかったり、自然と情報を集めたくなるような感情の動きがベースにあります。例えば、好きなアイドルやアニメについて語るとき、特別な努力をしなくてもテンションが上がるような、あの感覚です。
一方の「得意」は、より“成果”に近い概念です。知識やスキルがある、他人から評価されやすい、短時間で仕上げられる、などの要素が絡みます。自分ではあまり実感がなくても、他人から「これうまいね」と褒められるテーマがあれば、それは“得意”の可能性が高いと言えるでしょう。
もちろん、好きなことが得意でもあるというケースもあります。しかし実際には、好きだけど苦手、得意だけど興味が湧かない、といったズレが生じることのほうが多く、それがジャンル選びを難しくしている要因でもあります。
まずは、「好き」と「得意」を別物だと考えるだけでも少し気持ちが楽になるかもしれません。
「好き」でも疲れる理由
「好きなことなら、ずっと書いていられるはず」
そんな期待とは裏腹に、好きなテーマに向き合うほど、かえって疲れてしまうことがあります。その背景には、いくつかの“落とし穴”が潜んでいます。
まず1つは、「正しさ」への過剰なこだわりです。好きなジャンルほど情報量も豊富で、自分の中に「これはこうあるべきだ」という絶対解的な理想像が強くなりがちです。そのため、書く際にもリサーチに時間がかかったり、「この表現で合っているのか」と不安になって、筆が止まってしまうことがあります。
また、好きなテーマはどうしても“自分の感情”が強く出やすくなります。主観がにじむ文章は共感を呼ぶ一方で、フィードバックや批判がダイレクトに刺さり、自信を削られる原因にもなります。ときに、高く評価される文章ほど、強い批判の対象にもなりやすいもの。
特に、自分が強く思い入れを持っているテーマに対する否定的な声ほど、受け入れるのが難しく、心に深く残ってしまうことがあります。さらに、「うまく書けなかった自分」が許せず、自己否定のループに陥ることも。
その結果として、書くこと自体がプレッシャーになり、もともとは趣味として楽しんでいたはずのテーマが、だんだん苦しいものに変わっていってしまう…。好きだからこそ、手を抜けず、完璧を求めてしまう、そしてその完璧主義が、結果として書くエネルギーを削ってしまうのです。
つまり、「好き」だからといって、それがイコール「楽に書ける」「続けられる」ではないという現実があります。むしろ、気持ちが入りすぎるテーマほど、意外と疲れやすいということを知っておくことが大切です。
「書けるけど疲れる」と「書いてて楽しい」どちらを選ぶべき?

ライターとして活動していると、さまざまなジャンルの仕事に触れる機会があります。その中には「サクサク書けるけど、なぜかどっと疲れるテーマ」や、「時間はかかるけれど、なぜか心地よく筆が進むテーマ」など、書き味がまったく異なるものが存在します。
いったい、どちらを選ぶのが正解なのでしょうか?
効率よく書けて収入につながるジャンルを優先するのか、それとも、やっていて楽しいと感じられるジャンルを大切にするのか。これは、ジャンル選びにおいて多くのライターが直面する問いの1つです。
ここでは、「短期の効率」と「長期の継続性」、そしてその間にある“ちょうどよさ”について考えていきます。
短期の「効率」か、長期の「継続性」か
「書けるけど疲れる」ジャンルは、短期的に見ると非常に効率がよく、収入にも直結しやすい傾向があります。リサーチの手間が少なかったり、テンプレート化された構成で進めやすかったりと、作業時間あたりの成果が出やすいため、特にフリーランスでライターをやっている方にとっては魅力的に感じられることもあるでしょう。
しかし、心身への負荷が高いテーマは、続けるほどに摩耗していきます。「またこのジャンルか…」と気持ちが重くなり、モチベーションの低下や燃え尽き感につながるリスクも無視できません。
一方で、「書いてて楽しい」と感じられるジャンルは、時間こそかかるものの、精神的には比較的負担が少なく、執筆そのものが“気晴らし”になることもあります。ただし、必ずしも単価が高かったり、需要が多かったりするとは限らず、収入とのバランスが課題になることもあります。
このジレンマに対して、どちらを選ぶべきかは、一律の正解があるわけではありません。
例えば、駆け出しの頃で実績を積みたいときや、生活の安定を優先したいときは「効率重視」の選択が現実的となるでしょう。逆に、ある程度ベースの収入が確保できていて、将来の方向性を模索したい時期であれば、「楽しさ」や「書きやすさ」に軸足を移す選択も視野に入れてみるのが良いかもしれません。
ジャンル選びは、単なる“向き・不向き”ではなく、その時々のキャリアフェーズや心身の状態とも密接に関わっています。だからこそ、「今の自分にとって、どちらが負担が少ないか」「どちらの選択が、あと3か月後の自分を助けてくれるか」と、色々な観点から定期的に振り返ってみてください。
中間領域を探すという選択肢
「好きだけどしんどい」「得意だけど気が乗らない」、この二択で考えてしまうと、ジャンル選びはどうしても苦しくなります。そこで筆者から提案したいのが、「まあまあ好き」で「まあまあ得意」な、“中間領域”を軸にするという考え方です。
熱狂するほどではないけれど、そこそこ興味が持てて、最低限の知識もある。書いていて気持ちがラクで、そこまでストレスを感じずに仕上げられる。そんなジャンルは、一見地味に思えるかもしれませんが、実は「長く、安定して続けられる」という点で非常に優れています。
完璧を目指すと、それに見合う労力や時間が必要になります。特に“好きすぎるジャンル”では、つい100点を目指してしまいがちですが、毎回全力投球していたら心がもちません。むしろ、「70点くらいで、無理なく書ける」ジャンルを軸にすることで、アウトプットの質と量を安定させやすくなります。
この“疲れにくいジャンル”こそが、ライターとして長く走り続けるための安心材料になります。また、最初はピンとこなくても、実績が積み重なり、フィードバックを通じて手応えを感じるようになることもあるでしょう。
「好き」や「得意」を過度に理想化するのではなく、「ちょうどいい距離感」で向き合えるジャンルを探す。ジャンル探しの軸を少し見直すだけでも、迷子から脱することができるかもしれません。
筆者が「続けられるジャンル」に出会うまでの話

ここまで「続けられるジャンル」の見つけ方についてお話ししてきましたが、筆者がいかにしてこの考えに至ったのか、ちょっとだけ自分の話をさせてください。
私はもともと、「好きなことを書いて食べていきたい」と思ってライターになったタイプではありませんでした。そもそも“好きなこと”が多すぎて、1つに絞れなかったんです。映画も音楽も漫画も教育も語学も…なんでも興味があって、むしろ「何が一番好きなのか」を決めるほうが難しかった。
だからライターとして活動を始めた頃は、「ちょっと興味がある」「なんとなく知ってみたい」と思えるジャンルを軸にして、いろんな案件を受けていました。大人になると時間に制限があり、勉強の時間もなかなか取れないので、仕事をしながら勉強ができる感覚でとても楽しかったです。
とはいえ、毎日違うテーマを書き続けていると、だんだん「私は何が得意なんだろう?」と自分の輪郭がわからなくなることもありました。「尖った専門性がない自分は、やっぱり中途半端なのかな」と、劣等感を抱く時期も正直ありましたし、今でもあります。
でも、その中で少しずつ気づいたことがあります。それは、「好きなこと」よりも、「自分の想像が届く範囲」のジャンルのほうが、書きやすくて続けやすいということ。
例えば、筆者は一時期、ワーキングホリデーに関しての案件に携わらせてもらうことがありました。ワーキングホリデーの経験はありませんが、「英語」「留学」「キャリアアップ」といったテーマは、前職で英語コーチングに携わっていた自分にとって親和性があります。
直接の経験がなくても、過去の知識や感覚を活かして書ける範囲なら、リサーチも苦にならないし、自然と文章に説得力が出る。逆に、自分の想像力が及ばないテーマだと、いくら調べても要点がつかめず、筆が止まりがちでした。
だから今は、「ものすごく好き」や「圧倒的に得意」でなくても、無理なく手が動くジャンル、自分の中で自然に言葉が湧いてくるようなテーマを大切にしています。少し余白を残せるくらいの距離感のほうが、気持ちに余裕が生まれて、安定したアウトプットにもつながると感じているからです。
そして、「本当に好きなこと」は、お金や納期に縛られない場所——noteやSNSなどで自由に書けばいい、そう割り切るようになってから、ライターという仕事との向き合い方がぐっと楽になった気がします。
まとめ|好きなだけじゃ続かない。疲れないジャンルこそが武器になる
「好きなことを書いて生きていきたい」という気持ちは、多くのライターにとって原動力となります。情熱があるからこそ、リサーチも深掘りできるし、言葉にも熱がこもる。
でもその“好き”が強すぎると、ときに自分を追い込み、書くこと自体がつらくなってしまうこともあります。
一方で、「得意」は継続する力になります。自分の中にある知識やスキルを活かして、無理なく、安定して書けるテーマ。一見地味に思えても、“仕事として”ライターを続けていくうえで非常に心強い存在となるでしょう。
だからこそ、「好き」と「得意」のバランスをどう取るかが大事です。特に、“書いていて疲れない”という感覚は、とても大切な指標になります。書いていて自然体でいられる、自分のペースで言葉が出てくる、そんなテーマと出会えたなら、それはきっと長く付き合えるジャンルになるはずです。
ジャンル選びに正解はありません。でも、自分の“書く体力”や心の余裕に合ったテーマを少しずつ見つけていくこと、無理なく続けられるスタイルを探していくこと。それが、ライターとしてのキャリアを無理なく、続けていくための土台作りになるのではないでしょうか。
この記事を書いたライター
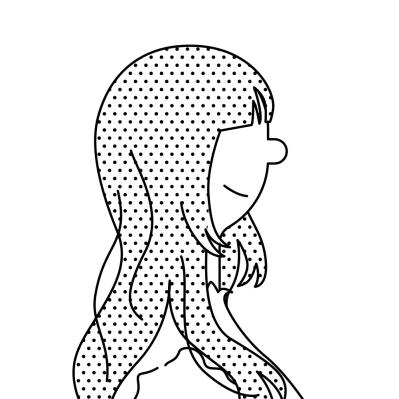
Haruka Matsunaga
おしゃべりが止まらない5か国語話者ライター。二次元にも三次元にも推しがとにかく多すぎるオタク。素敵なものや自分の好きなものをとにかくたくさんの人に広めたいという気持ちが執筆のモチベーションです。ペンは剣より強し、言葉の力を信じて...