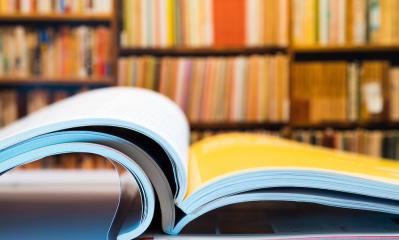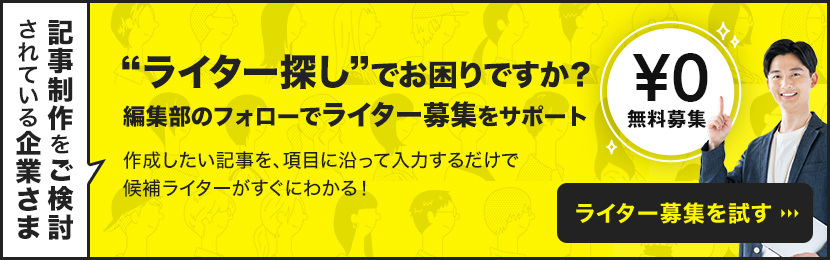人に伝わる文章を書くには意識したいポイントがある

人に伝わる文章と言っても、書くのは難しいものです。ライターの方の中には、いつも悩みながら書いている方もいるでしょう。
まずは書き方について触れる前に、以下の2つについて知っておきましょう。文章を書く際の基本となる部分です。
- 文体を意識する
- 技術と精神の両方からのアプローチが必要
文体を意識する
ライターとして文章を書く場合、最も意識したいのが文体です。ここで言う文体とは、「です・ます調」ではなく、媒体によって求められる文章の形を指します。以下のようにわけてみましょう。
- ライティングやコピーライティング
- シナリオライティング
- ブログ
- 小説
これらの中で、一般的に上へ行くほど個性が不要で、下へ行くほど個性が必要です。小説家はその極地とも言えます。
一方で、Webライティングを含めたライターとしての仕事は、個性が不要です。クライアントが欲しいのは読者が納得し満足できる記事なので、ライターの個性を入れては余計なノイズになってしまうのです。
そのため、人に伝わる文章を書く際は、まずどの媒体で書くのかを把握しておく必要があります。
技術と精神の両方からのアプローチが必要
人に伝わる文章を書くには、技術だけでも精神だけでもダメです。その両方が必要になります。
どれだけ人に伝えたい想いがあっても、技術が無ければ思うように伝わりません。一方で、どれだけ人に伝えられる技術があっても、想いが無ければ読者の心を動かせません。
技術と熱意、その両方があって、初めて人に伝わる文章になります。
これはライティングだろうとシナリオだろうと小説だろうと、変わりません。片方の車輪しかない車がうまく走れないのと同じように、技術と精神の両方を使ってようやく人の心を動かせます。
【技術編】人に伝わる文章の書き方4選

人に伝わる文章の書き方として、まず意識したいのが技術です。日本語が最低限できているのは当然として、そこから一歩進んだ技術を以下に分けて解説します。
- 視点を統一する
- フレームワークを使う
- SEOを意識しすぎない
- 読者にストレスを与えない
視点を統一する
ライティングにおいて、視点を統一するのは大切です。視点が定まっていると、伝えたい内容がブレずにすみます。ターゲットを明確化する理由の1つです。
記事原稿などを書く際、まずターゲットを決めてから書き始める方が多いかと思います。構成案が既にある場合は、想定ターゲットが書かれているはずです。
記事は、そうしたターゲットの視点に立って書くようにします。例えば、「iPhone17が欲しい22歳の新卒」がターゲットなら、記事全体をその視点に合わせます。急に販売店側の視点を出してはいけません。
当たり前だと感じる方も多いかとは思いますが、想像以上にできていないものです。文章を書く土台を作るつもりで、一度振り返ってみましょう。
フレームワークを使う
人に伝わる文章を書くのに使いたい技法として、フレームワークがあります。中でも使いやすいのが、多くの方が1度は聞いたことがあるであろう、以下のものです。
- PREP法
- PASONAの法則
PREP法は、読みやすい文章を書くのに適した文章として有名です。多くの場面で使われていて、小説でも活用している作家さんが多くいます。
一方のPASONAの法則は、コンテンツマーケティングで良く利用されるフレームワークです。CTA(Call To Action/行動喚起)例えば「資料請求」「購入はこちら」などの読者に行動を促す部分の直前で使うと、効果を得やすい文章が書けます。
フレームワークは、人に伝わる文章を書ける最も簡単な技法です。使わない手はないので、積極的に導入しましょう。
SEOを意識しすぎない
SEOライティングをしていると、つい意識してしまうのがSEOです。Webの記事を書くと意識せざるを得ない部分ですが、SEOばかりに意識を向けると、人間にとって読みにくい文章になってしまいます。
例えば、同じキーワードを不自然に繰り返したり、検索結果に上げることを優先して不自然に見出しを増やしたりすると、文章の流れやリズムが崩れてしまうためです。
SEOはあくまでもSEOです。Googleもユーザーを第一に考えたコンテンツの作成を推奨しているため、意識しすぎない方が良いでしょう。
ただし、クライアントのレギュレーション次第では、SEOを意識しすぎた文章になる場合があります。そのような場合は腕の見せ所と思って、ゲーム感覚で文章を書くと楽しみながら表現力を向上できます。
参照:Google「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」
読者にストレスを与えない
人に伝わる文章を書く際に意識したいのが、「読者にストレスを与えない」という点です。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。
- 同じ語尾を連続で使わない(ますは2回まで、ですは1回まで)
- 誤字脱字をゼロに近付ける(なしが理想)
- 視点ブレを起こさない
- 同じ位置に段落を挟んで同じ文字を使わない
- 「形容詞+です」を使わない
語尾を連続で使わないのは、多くの方が意識しているかと思います。誤字脱字も同じです。理想はゼロですが、難しいのも事実なので、目視+校閲ツールでゼロに近付けましょう。
視点ブレに関しては、先述した通りです。ターゲットとしている読者の視点を最後まで使ってください。
一方で、ついやってしまいがちなのが、後半の2つです。同じ位置に段落を挟んで同じ文字を使わないというのは、文頭に同じ文字を使った文章を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。以下のように視認し辛い文章になります。
ーーーーーーーーー
【例】
iPhone17は2025年に発表された最新のiPhoneです。
iPhone17に変更すると、16よりも綺麗な写真を撮影でき、ズームしても画像が劣化しません。
ーーーーーーーーー
冒頭に「iPhone17」が連続しているので、パッと見た瞬間に読みにくいと感じます。例では冒頭なのでわかりやすいのですが、本文中となると段落や改行によって、思いがけない形で同じ文字が重なる場合があります。なるべく散らして、視認性を向上させましょう。
「形容詞+です」も同じです。「多いです」のような表現は、読者に幼稚な印象を与えてしまいます。
参考:「形容詞+です」は原稿執筆において適切か?現役編集者の見解(文亭 - fumitei -)
こうした読者がストレスを感じる部分は、ライターならできるだけ排除しておきたいポイントです。スムーズに読めるよう工夫を凝らしていきましょう。
作成してから時間を置く
納期がギリギリでない限りは、なるべく納品まで時間を置くのも大切です。推敲する際にフラットな視線で見られるようになります。
書き上げてすぐは「最高の記事(作品)が書けた」と誰しもなりますが、時間を置くとほとんどの場合で「なんだこのひどい文章は!」と感じるものです。書き上げた当初にあった達成感がなくなり冷静になるため、起こります。
この状態で文章を推敲すると最も修正しやすいのですが、納期の関係上、難しいケースもあるでしょう。そのような場合は、以下の方法が効果的です。
- 記事原稿を紙に印刷してチェックする
- 腕を組むなどをしてモニターとの間に壁を作る
紙に印刷してチェックする方法は、出版社でも取り入れています。紙に印刷して読むと、モニター画面よりも誤字脱字や不自然な表現に気づきやすくなります。媒体が変わることで、文章を新鮮な目で見直せるからです。私も出版社時代、何度もやりました。
また、カナダのメディア批評の先駆者であるマーシャル・マクルーハンは、以下のように定義しています。
- 紙に印刷:反射光を利用して文字を読むため脳が「分析モード」に切り替わる
- 画面を見る:透過光を利用して文字を読むため脳が「パターン認識モード」に切り替わる
脳の仕組みとして、紙に印刷すると目に入る情報を一つひとつ集中してチェックできるため、間違いを発見しやすくなるのです。対してモニターでの確認は、脳は送られてくる情報をそのまま受け取るため、細かい部分を多少無視しながら、全体を把握しようとします。
この違いが、誤字脱字を見逃してしまう仕組みの1つと考えられています。科学的な根拠はありませんが、実感している方が多い方法なのも事実です。原稿をフラットな視線で見る方法の1つとして、実践してみるのも良いでしょう。
とはいえ、毎回印刷していては紙代やインク代も馬鹿になりません。そこでおすすめなのが、腕を組むなどをしてモニターの間に壁を作る方法です。記事原稿との間に壁ができるので、フラットな視線でチェックしやすくなります。
【精神編】人に伝わる文章の書き方4選
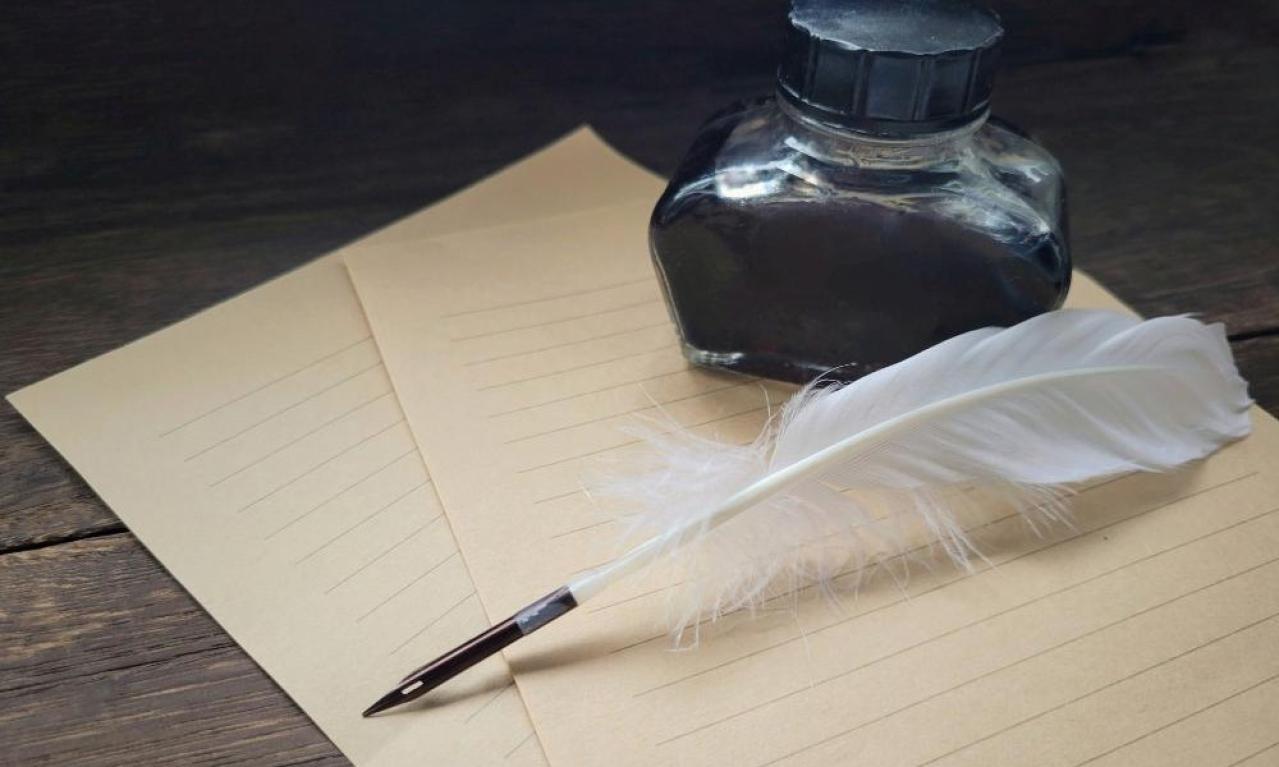
人に伝わる文章を書く技術がわかったところで、次に精神的な部分にも触れていきましょう。「技術さえあれば十分じゃない?」と思う方もいるでしょうが、実は精神的な部分も大切です。特に以下の4つのポイントは意識してみてください。
- 熱意を込める
- 共感できるポイントを作る
- 本当に伝えたい内容を明確にする
- 自分が読んで心を動かされる文章を書く
熱意を込める
まず意識したいのが、熱意を込めるということです。熱意のあるかないかで、その文章から受けるイメージは大きく変わります。
例えば、熱意はないがガジェットについて詳しく書いている記事と、技術はないがガジェットに感動した気持ちがこもった記事だと、後者の方がより読者の心を動かします。
人に伝えたい熱意がこもっているからです。同じような事例として、営業が自社の商品を愛しているかどうかで成績が変わるといったケースもあります。
私たちライターが文章を書くときも同じです。クライアントの気持ちを汲んで、読者に熱意が伝わるように書かなくてはいけません。そのためにも取り上げる内容について詳細に調べ、自分事として発信できるようにしましょう。
共感できるポイントを作る
人に伝わる文章を書く際に大切なのが、共感できるポイントを作ることです。読者に「あ、これ自分のことだ!」と感じてもらうのです。
ターゲットの掘り下げなどでしている方も多いかとは思いますが、文章の中にも共感ポイントを散りばめていきましょう。特にWebライティングでは、導入文に共感できるポイントを作れるかどうかが重要です。
難しい場合は、ジャパネットたかたのテレビショッピングを見てみましょう。共感できるポイントを学べる最高の教材です。なぜなら、視聴者の悩みや「そこが気になる!」という気持ちを代弁しながら商品を紹介しているからです。相手の立場に立って語る姿勢や表現は、共感を生む文章づくりのお手本になるでしょう。
本当に伝えたい内容を明確にする
Webの記事を読んでいると、中には「で、これは何を伝えたいの?」という記事に出くわし方も多いのではないでしょうか。
そのような記事は、伝えたい内容を明確化できていないケースがほとんどです。ターゲットに何を伝えたいのかという、軸のようなものが設定されていません。
例えば転職メディアでの記事を作成する場合、クライアントが「自社サービスを使って転職して欲しいのか」「利用者のキャリアをサポートしたいのか」によって伝えたい内容が変わります。
前者であれば自社サービスを使う良さですし、後者であれば自社サービスへの相談です。
こうした軸になる部分は、記事全体としてはもちろん、見出しごとにも当てはまります。SEOを意識していると、見出しを受けて「AもあるけどBもあるし、Cも補完しなきゃ!」となりがちですが、そうすると本当に伝えたい内容がブレてしまいます。
結果として読者にとって読みにくい文章になるため、まず本当に伝えたい内容を明確にし、脱線しないように意識しましょう。
自分が読んで心を動かされる文章を書く
人に伝わる文章を書く際に意識したいポイントとして、自分が読んで心を動かされるかも大切です。最も近い読者は自分なのですから、自分の心が動かなければ他人の心を動かせるわけがありません。少なくとも自分の心が動けば、近い感性を持っている人は同じように感動してくれるはずです。
これは特に小説やシナリオライティングの世界では効果が大きく、以下のような使われ方がされます。
- 泣けるシーンを読んで自分が泣けるか
- アダルトシーンを書いて興奮できるか
- ドキドキワクワクできる冒険になっているか
かく言う私も、泣けるシーンを書きながら号泣したことがあります。画面がぼやけて何も見えず、シーンを書き切るのに時間がかかりました。
先述した「熱意を込める」にも近しい部分があるのですが、心を動かされる文章には大なり小なり力があります。
人を動かすライティングをするのなら、ぜひとも身につけましょう。
人に伝わる文章が書けるライター/物書きになろう!

人に伝わる文章は、技術を身につければ身につけるほど、難しくなっていきます。技術が先行しすぎて、バランスが悪くなるためです。そのため、熱意や共感といった精神的な部分も必要になります。
技術と精神の両方を均等に使うのは難しいのですが、習得できれば強い武器になってくれます。誰かの心を動かせる文章を書けるように、日々精進していきましょう!
この記事を書いたライター
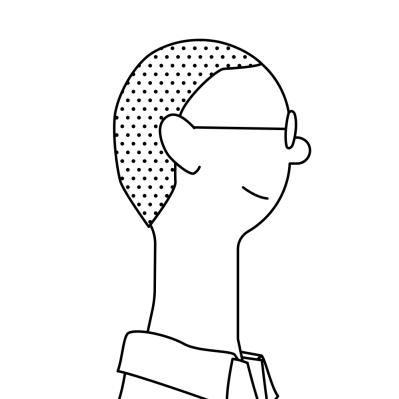
諸道秀忠
滋賀県生まれ滋賀県育ちの「三方良し」がモットーのライター/作家。たまに専門学校の講師も。アニメ・ゲーム・小説には目がない親指シフターです。書くことが好きなので、SEOライティングから小説まで幅広く書いています。得意ジャンルはIT・ガ...