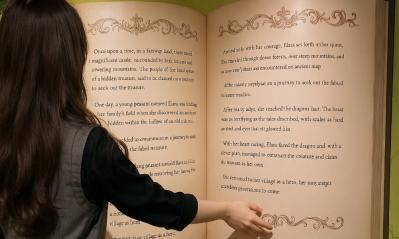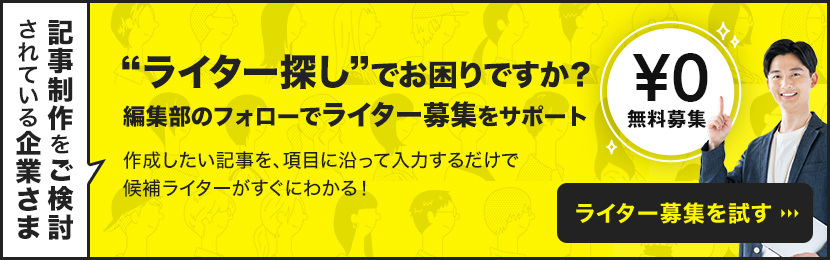テストライティングには2種類ある?

ライターを始めて間もない頃、テストライティングには大きく分けて2つのパターンのテストライティングがあると知りました。
それは、“課題として与えられる模擬課題型”と、“実際の案件で試される実案件型”があるということです。
一見似ているようで、書き手として感じるプレッシャーや難しさ、得られる学びがまったく違っていたのです。
模擬課題型テストライティングの体験談
私が最初に経験したテストライティングは、“模擬課題型”といえる形式でした。
内容自体は実際の案件に非常に近く、書くテーマも具体的でしたが、使われている情報はすべて架空のものでした。
その課題は、とあるハンドメイド講座の紹介記事の執筆です。講座の概要・特徴などが簡潔にまとめられた資料をもとに、魅力的な紹介文を構成・執筆してくださいという内容でした。
この課題のポイントは、与えられた情報から“何をアピールするか”を自分で考える必要があるところです。
私は「どんな読者にとってこの講座が魅力的か?」を想像し、読者像を明確にしてから、訴求ポイントを見出しに落とし込んでいきました。
構成や表現に自由度が高い分、「これで本当に合っているのかな…」という不安が残ります。何度も構成を練り直し、文章を読み返しながら、想定した読者に「申し込みたい!」と思ってもらえるような流れを意識して仕上げました。
提出後、フィードバックは特にありませんでしたが、結果的に合格の連絡をいただくことができました。
自分なりに工夫したポイントが伝わったのかもしれないと、少し自信につながったのがよかったです。
模擬課題型のテストでは、「指示通りに書く」よりも「自分で考えて構成・提案する力」が求められているように感じます。キーワードだけを与えられ、リサーチ力を試されることもあります。
フィードバックがない場合でも、書いた分だけ確実に自分の力になっていると実感できる経験でした。
実案件型テストライティングの体験談
もう一つのテストライティングは、「実案件型」と呼べるものでした。応募後、クライアントから提示されたのは、実際に納品予定の原稿を“テスト価格”で執筆するという条件です。文字単価は通常1.5円のところ、テスト時は1.2円での実施でした。
案件の詳細については守秘義務の関係上、控えさせていただきますが、このとき私が担当したのは、1記事10,000文字というボリュームのある記事でした。
それまでに書いたことがあったのは、せいぜい3,000文字程度です。
「いきなり1万字!?」「本当に仕上げられるのかな……」と、不安とプレッシャーでいっぱいでした。
執筆期間として約1週間が想定されていて、余裕があるようにも感じられましたが、情報量が非常に多く、リサーチにもかなりの時間を要しました。結局リサーチと執筆に予想以上の時間がかかり、予定していたスケジュールではまったく終わらず、夜中までパソコンに向かって作業する日が2日続きました。
今思えば、自分の実力や執筆スピードがまだ足りなかった部分も多く、かなり無理をしてしまったなと思います。それでも「どうにか間に合わせたい」「せっかくもらえたチャンスを無駄にしたくない」という一心で、なんとか仕上げて納品しました。
結果的には、ディレクターから丁寧なフィードバックをいただき、クライアントからも好評だと採用の連絡をいただくことができました。
完成度を100点とするなら、自分の感覚では「60点くらいかな」と思っていたので、驚きと安堵が混ざった気持ちでした。
この実案件型のテストでは、「納期までに仕上げる力」「構成に沿って正確に情報を整理する力」「ある程度の粘り強さ」が試されていたのだと思います。
まさに“実践の場”であり、実務に耐えうるかどうかをリアルにチェックされている印象でした。
模擬課題型と実案件型、体験してわかった違い

テストライティングにはさまざまな形式がありますが、私が体験したのは「模擬課題型」と「実案件型」の2種類でした。
どちらも特徴や求められるスキル、難しさに違いがあり、実際に経験してみて多くの気づきを得ました。
まず、模擬課題型は架空の講座を題材にしたもので、資料から自分で訴求ポイントを考え、自由に構成して記事を書くスタイルでした。自由度が高い分、自分で企画力や構成力を発揮しなければならず、正解が見えにくい難しさがあります。
フィードバックはなく合否連絡のみでしたが、自分なりに工夫した部分が評価されたと思います。
一方、実案件型は実際に公開予定の案件そのままに、文字数や納期が明確に示されています。私の場合は1万字の大ボリュームで、構成から入稿まで一連の流れをすべて実案件そのままに実施しました。ここでは、正確に情報を整理し、構成に沿って納期を守る力が試されます。
報酬が支払われることもあり、責任感を持って取り組めるのが特徴です。ディレクターさんからのフィードバックも丁寧で、改善点が具体的に示されました。
両者は求められる力やテストライティングの形式が異なりますが、どちらも大きな学びがありました。
実際に体験してみて、テストライティングは「形が違うだけでなく、自分の成長に直結する大切な通過点」だと感じています。
テストライティング経験から得た大切なこと

テストライティングは、未経験や初心者ライターにとって特に緊張する場面ですが、怖がらずに挑戦することが何よりも大切だと感じました。
私も最初は不安や焦りがありましたが、経験を積むうちに「テストに進めることは案件に挑戦するチャンスを得ること」と考えるようになりました。
今回は良い返答を得られた時の例を挙げましたが、実際は何十倍もの数の案件に応募し、応募文やテストライティングで不採用の通知を貰っています。
テストライティングでは、合否だけに一喜一憂しないことが大切です。落ちたとしてもそれが実力不足を意味するわけではなく、案件との相性やクライアントの好みも影響します。
書くことで得られる「書く感覚」や「課題への対応力」が、あなたの成長につながると考えてください。
また、納期管理や自己管理の力も試される場面です。特に実案件型では、実務のペースをつかむ良い機会になるため、計画的に作業を進める必要があります。
最後に、何よりも「挑戦する気持ち」が最も価値ある財産になると私は感じています。
初めてのテストは怖くても、一度経験すれば次からは必ず慣れていきます。挑戦を続けながら、自分のスタイルや強みを見つけていってほしいと思います。
この記事を書いたライター

ふろっぴ
大阪在住、小学生と幼稚園児を子育て中のママライターです。「子育てだけで自分の人生半分終わらせたくない!」と思ってWebライターのお仕事を始めました。読者目線を第一に丁寧な執筆を心がけています。色々なジャンルに挑戦中!ハンドメイド制...