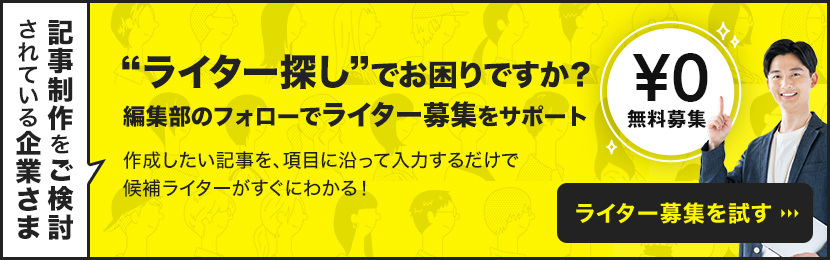だらだら長くなっていない?1文はスッキリ短く
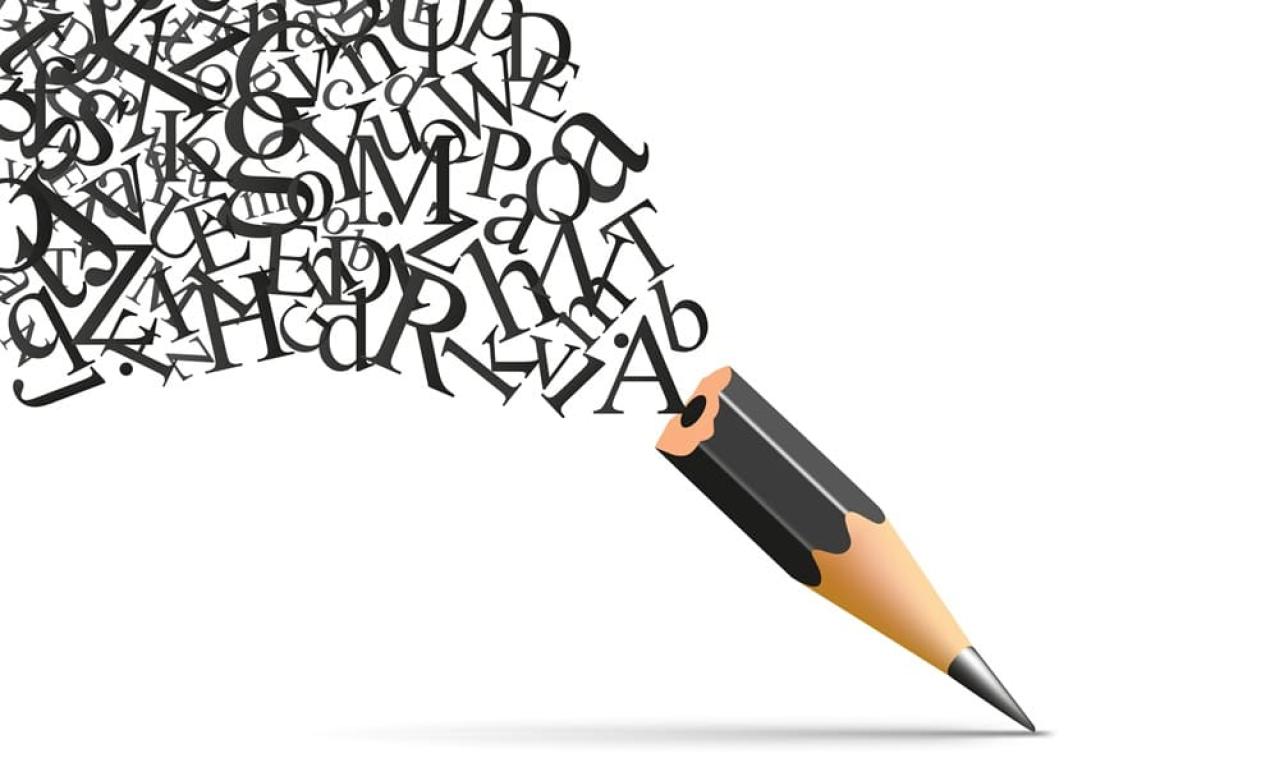
私が現在働いている美容メディアの社長の講座を受けているときに、最初に取り組んだのは簡潔な文章を書く訓練でした。
一般的に、1文は60文字以下に区切るのがベストといわれています。1文が長すぎると内容がわかりにくくなり、読み手に負担を与えてしまうからです。
具体的な文章を例に挙げて説明します。
「私は子どもの頃からライターになりたいと思っていて、大学では日本語学科を選択し、できるだけ多くの言葉を触れることを心がけて過ごして来た結果、今こうしてライターの仕事をしています」
この文章には区切りである句点がないため、だらだらと文章が続いて読みづらい印象を与えます。
次は、この文章に読みやすくなるよう区切りを意識して入れてみました。
「私は、子どもの頃からライターになりたいと思っていました。大学時代に心がけていたことは、日本語学科でできるだけ多くの言葉に触れること。その結果、今こうしてライターの仕事に就いています」
似たような文章でも、適切に句読点を入れるとスッキリとした印象になりますよね。ただし、読点の使いすぎには気を付けましょう。目安としては、60文字程度の文で1~2回の使用が最適です。
また、文章を書く際に気をつけてほしいのが、構造を複雑にする「~が」の多用です。これを繰り返すと、文章が冗長になりやすいので極力避けるようにしてください。
ほかにも、文章をスッキリさせるには、不要な接続詞を省くのも効果的です。なくても意味が通じる場合は、なるべく使わないよう意識しましょう。具体的には「だから」「それで」「そこで」が該当します。
下記の例文で解説しますね。
「昨日の朝は雨が降っていました。だから、私は外出を控えました。しかし、午後は天気が回復したので、買い物に行きました。そこで、まずスーパーに寄って食材を買い、その後、本屋さんに行きました。その後、夕方は友人とカフェで待ち合わせをして、一緒にカフェラテを飲みました。結果的に、充実した一日を過ごすことができました。しかし、帰宅後は疲れが出て、すぐに寝てしまいました」
少し窮屈な印象に感じませんか?この文章の接続詞を省き、読みやすくしてみました。
「昨日の朝は雨が降っていたため、私は外出を控えました。しかし、午後には天気が回復したので買い物へ。スーパーで食材を買い、本屋さんにも立ち寄りました。夕方は友人とカフェで待ち合わせ、カフェラテを飲みながらゆったり過ごしました。充実した一日で、帰宅後は疲れが出てしまいすぐに寝てしまいました」
このように、接続詞を省くと文章がスッキリした印象になります。
ただし、逆説的な意味を持つ接続詞「しかし」「とはいえ」「だが」といったものは、使わないと前後の関係性や意味が変わってしまう場合があります。必要な接続詞は省かないようにしましょう。
うっかりやってしまいがち!二重表現に気をつけて

記事を書いているとうっかりやってしまいがちなのが、二重敬語、二重否定、二重表現です。
二重敬語は、1つの言葉に2つ以上の敬語をつけてしまう表現のこと。例にしてあげると「ご予約を承りいたしました」ではなく「ご予約を承りました」が適切です。
二重否定は、否定の言葉を連続で使うことです。例にしてあげると「私の責任といえなくもない」より「私の責任といえる」の方が明確でしょう。否定の言葉を連続で使うと、どういう意味なのか読者は混乱してしまいます。
二重表現は、同じ意味の言葉を重ねて使う表現です。例にしてあげると「一番最初」「頭痛が痛い」「返事を返す」など、日常生活で使ってしまいがちな表現です。二重表現はチェックするときにさらっと見逃してしまいがちなので、気になったら校正ツールで調べてみてください。
「あれ?この表現って何かおかしくないかな?」って書きながら疑問に思い始めたときは、Webライターとして成長した証ですよ!
後回しにしないで!結論から先に書こう
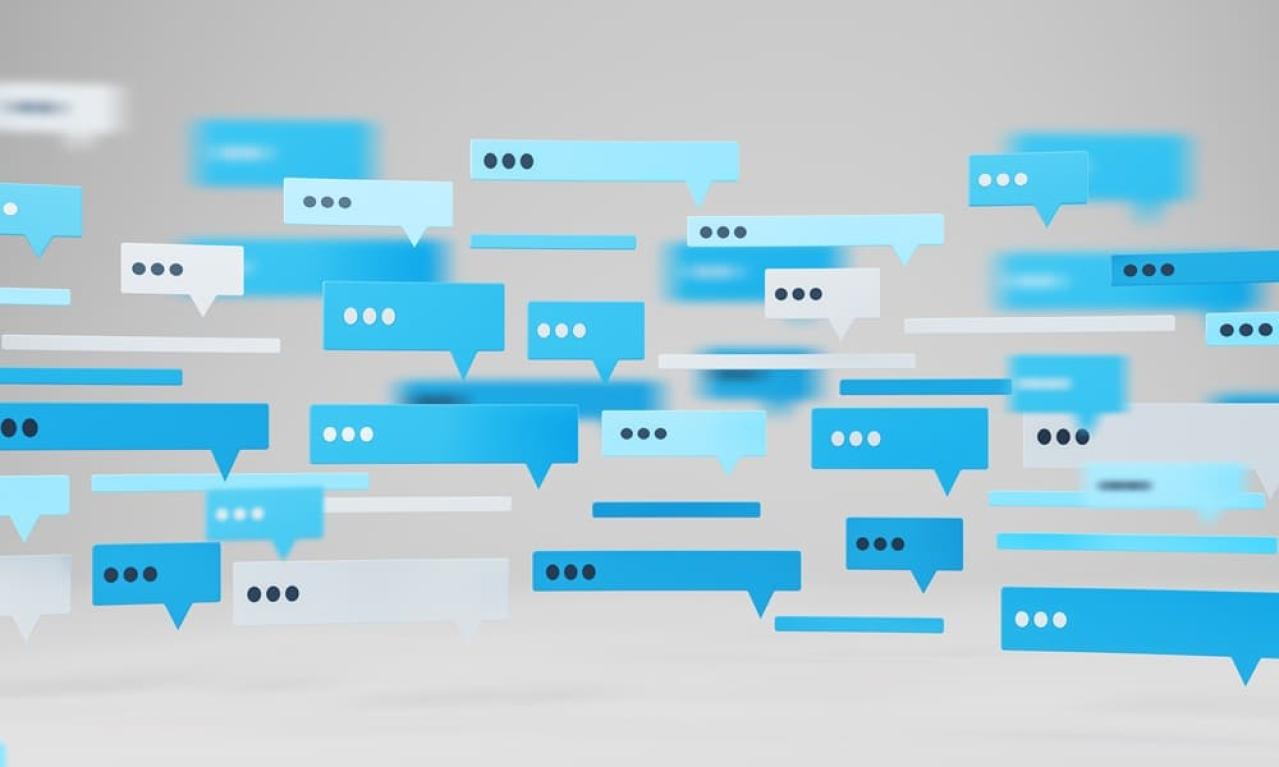
結論から先に書く文章法に「PREP法」と呼ばれるものがあります。
PREPとは、以下の頭文字を取ったものです。
- Point(結論)
- Reason(理由)
- Example(具体例)
- Point(結論)
結論、理由、具体例、さらにもう一度結論を繰り返すことにより、書き手の意図が読み手に的確に伝わります。
以前私が書いた縮毛矯正に関する記事を例にして説明しますね。
Point(結論):「髪の毛のボリュームやうねりが気になる方におすすめのメニューが縮毛矯正です」
ここでは、読み手の興味や関心を引くように何について書くか説明をします。
Reason(理由):「縮毛矯正は、頑固なくせ毛やカールの強い天然パーマの髪の毛もストレートヘアにでき、扱いやすくなります」
ここでは、なぜそのことについて書くのか、どうしてそういわれているのかの理由について説明します。
Example(具体例):「朝のスタイリングに時間がかかる、湿気が多いと髪が広がってしまうと悩んでいた方が、縮毛矯正を受けて梅雨時でも快適に過ごせるようになったという声があります。縮毛矯正は特に髪の毛が扱いづらい、スタイリングが苦手という方におすすめです」
具体例は、文章の中でも多くの文字数を割くべき部分です。実際のエピソードなどを盛り込むと読者の共感を得やすく、記事の満足度を高める効果があります。
Point(結論):「自分にぴったりの縮毛矯正を見つけて梅雨の季節も快適に過ごしましょう!」です。
具体例を展開したら、最初に提示した結論と矛盾しないように再度主張を強調し、読者の行動を後押しします。
上司やクライアントに自分の仕事の進捗を報告するときにも、まずは結論から報告するのを意識するといいでしょう。
わかりやすい文章を書くと、ライターの世界はもっと広がる
今回はわかりやすい文章を書く工夫について紹介しました。わかりやすい文章が書けるようになると、Webライターとして働くだけではなく、会社員としても役に立ちますよ。
小手先のテクニックで記事を書くよりも、今回紹介した基本的なことを守るだけでいつもより記事の質が変わります。
これらのテクニックを実践して、あなたもわかりやすい文章を書くWebライターを目指してみませんか?
この記事を書いたライター

さき
会社員として働きながら、副業ライターをしています。美容、ライフスタイル、グルメ、地域創生の記事を中心に執筆。趣味はゲーム、食べ歩き、旅行です。旅行先のグルメや休日ランチなどの感想を記事に書いたりすることも。今後は新しいジャンル...