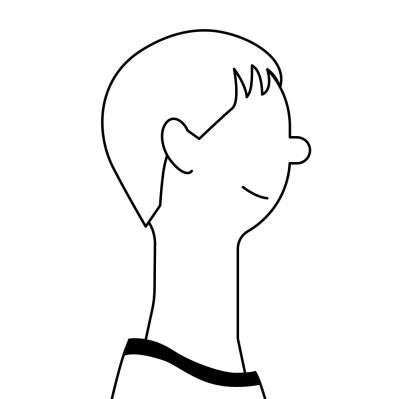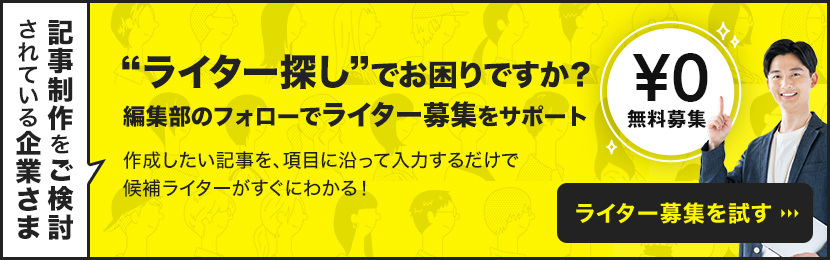秋になると「やる気が出ない」のはなぜか?

秋になると「集中できない・気力がわかない」などの症状が出る人が少なくありません。
以下に、秋に不調が起こりやすい主な要因を3つに分けて説明します。原因を理解できれば、自分のせいだと考える気持ちを減らし、具体的な対策を実施しやすくなるでしょう。
日照時間の減少で集中力が落ちやすい
秋から冬にかけて太陽の出ている時間は短くなっていきます。朝に光を浴びないと体内時計が遅れ、脳が朝を認識できません。日光を浴びる時間が減ると、眠りを整えるメラトニンがうまく働かなくなります。朝にだるさが残り、昼に眠気が強まり、夜は寝つきにくくなります。
ライターは、日光不足になりやすい室内を主な仕事場としています。起床したら、カーテンを開けて太陽の光を浴びるだけでも、体内時計の調整に効果はあります。
出典:快眠と生活習慣|厚生労働省
出典:眠り、リズムと健康②|NCNP病院国立精神・神経医療研究センター
日々の寒暖差・気圧変化で自律神経が乱れやすい
秋は、移動性高気圧と低気圧の影響が数日の周期で入れ替わり、日々の寒暖差が大きくなりやすい季節です。台風や低気圧で気圧も上下します。
気候の変化が続くと自律神経に負担がかかり、体調の不安定さにつながります。体温や血圧、呼吸を自動で調整するのが自律神経の働きです。
自律神経に負担がかかると、体温調整ができなくなり、疲労がたまりやすくなります。個人差はありますが、気圧が下がると血管が広がり、頭の重さやめまいを感じやすくなります。
自分の体の反応パターンを理解するには、天気とあなたの体調をメモしておくといいでしょう。傾向をつかんで、体調に合わせて予定を軽くすれば、心身ともに負担を減らせます。
出典:日本の天候の概説|気象庁
出典:大気圧の変化が安静時生理指標に及ぼす影響|日本生気象学会雑誌
ライターは生活リズムが乱れやすい
ライターは、夜の作業で寝る時間が後ろにずれると、太陽光を浴びる機会が減りがちです。日中に光を浴びないと体内時計が整わず、夜型の生活リズムが日常化してしまいます。
朝はだるさが残り、昼は集中できず、夜になってようやく作業が進むようになると、悪循環の始まりです。午前に進まないから夜に回そうとすると、生活リズムの乱れはいっそう深まります。
どうしても朝早く起きるのがつらい場合は、まずは決まった時間に起きるのが体調回復のための1歩です。
出典:概日リズム睡眠・覚醒障害(CRSWD)
うつ病経験ライターが続けている習慣

不調を抱えていても、生活習慣を1度に変えるのは難しいですよね。そこで、私が試し、今も続けている習慣を3つ紹介します。大がかりな準備は不要です。1つでも構いませんので、ぜひ実践してみてください。
朝に散歩する
朝に外へ出て光を浴びると、体内時計が「1日の始まり」を認識します。体は目覚めのリズムを取り戻し、夜に眠りやすくなるのです。
私も、かつては寝つきが悪く、昼間にだるさを引きずっていました。朝に歩く習慣を取り入れて以来、午前中から集中できるようになり、自然と仕事に入りやすくなりました。朝の散歩は天気が曇りの日でも効果があります。
出典:快眠と生活習慣|厚生労働省
起床後90分以上経ってからコーヒーを飲む
私たちの体は、起床の少し前からコルチゾール(ホルモンの1つ)が自然に増えて、目が覚めやすい状態になる仕組みを持っています。コルチゾールは、言わば「目覚めの朝スイッチ」です。
私は、自然な目覚めを活かしたくて、起床後90分以上経ってからコーヒーを飲むようにしました。コーヒーに入っているカフェインには眠気をおさえる働きがあるので、起床から時間をおきたいと考えたからです。それからは、午前中の集中力が安定し、午後の強い眠気も出にくいと感じています。
ただし「起床直後はカフェインの摂取を必ず避けるべき」と断定する公的な推奨はありません。効果には個人差があるため、コーヒーやお茶を飲む最適なタイミングは、あなた自身で調整してください。
夕方以降にカフェインを摂取すると、眠りの質を下げやすいので注意が必要です。カフェインに敏感な人は、最低でも就寝の5〜6時間前からコーヒーを飲むのは控えましょう。
出典:眠り、リズムと健康②|NCNP病院国立精神・神経医療研究センター
出典:快眠と生活習慣|厚生労働省
ガムをかむ
集中したいのに頭がぼんやりするときに、ガムをかむと、私は気持ちを切り替えられます。ガムを20分間リズミカルにかむと「血液中のセロトニン濃度が一時的に上昇した」という研究報告があります。セロトニンは、気分やストレスの調整に関わる神経伝達物質です。
研究では、脳内のセロトニンを直接測定したわけではありません。効果については確定できていないのが現状で、さらなる研究が必要です。
ガムを常備しておけば、すぐに集中スイッチを入れられるので、手軽な方法としてはイチ押しです。
出典:長時間のリズミカルなガム咀嚼はヒトにおけるセロトニン作動性下行抑制経路を介して侵害受容反応を抑制する|NLM
出典:チューインガムと健康:マッピングレビューとインタラクティブなエビデンスギャップマップ|NLM
出典:セロトニン(せろとにん)|厚生労働省
不調が続くなら医師に相談を

生活習慣の工夫で改善が見られる場合もありますが、長く不調が続くときは医療のサポートを考える必要があります。実際に私も、受診をきっかけに「うつ病」だとわかり、治療を受け心身の健康を回復できました。
私の体験をもとに、受診の目安や安心して受診するための方法をお伝えします。読んでもらえれば「医師に相談してもいい」と思えるようになり、不安を安心に変えられるでしょう。
2週間以上の不調が受診の目安になる
気分の落ち込みや不眠が2週間以上続いたら、病院への受診を検討してください。不眠や食欲不振、逆に過眠や過食などがあれば、注意が必要です。
私は医師に症状を細かく伝えることで、治療方針を調整してもらえました。小さな不調でも記録しておくと相談がスムーズになります。「こんなことを話していいのか」と迷っても、医師は情報を必要としています。気づいた変化を遠慮せず伝えてください。
体の不調から心の病気が見つかることもある
指の震えに悩んだのが、私が病院を訪れたきっかけです。始めは脳や首の検査などを受けましたが、数か月たっても原因はわかりませんでした。もちろん、不安は募るばかり。
それでも受診を続けて、不眠や気分の不安定さを伝えたところ、うつ病だと診断されました。心の相談を早い段階でしていれば、もっと早く不調の原因がわかった可能性があります。気にしすぎはよくありませんが、どんな些細な変化も軽く見ないでください。
薬の副作用は調整できる
病院での診断後は薬を処方されましたが、副作用が出た時期がありました。じっと座っていられない状態が続き、日常に支障をきたしたのです。症状を伝えたところ、原因は服用していた薬の1つだと医師が気づいてくれました。
薬は人の体質によって、合う場合と合わない場合があります。副作用が出ても自己判断で薬の服用をやめないようにしましょう。更なる悪化の原因となります。医師に相談すれば、適切な中止や変更ができ、症状を和らげられます。
「普段と違う症状がでた」と思ったら、ためらわず医師に伝えるのが、自分を守るために不可欠です。
まとめ|自分を責めずに、できることから始めよう
秋の不調は怠けではなく、光不足や気候の変化、生活リズムの乱れなどが重なって起きる可能性があるのです。背景を知れば「自分の弱さのせい」だと考えなくて済みます。
まとめとして再度、私が実践している習慣を示します。
- 朝に散歩する(外出が難しければ、窓際で日光を浴びるだけでも効果あり)
- コーヒーは起床後90分以上経ってから飲む
- 集中をしたいときはガムをかむ
あなたに合いそうな方法を1つ試すだけでもいいです。続けられない日があっても、自分を責める必要はありません。むしろ、あなたの心身を整える合図と考えてください。
やる気が出なかったり、集中できなかったりなどの症状が続く場合は、医師に相談するのも解決策の1つです。小さな行動から始めて、無理のない範囲で生活を整えていきましょう。