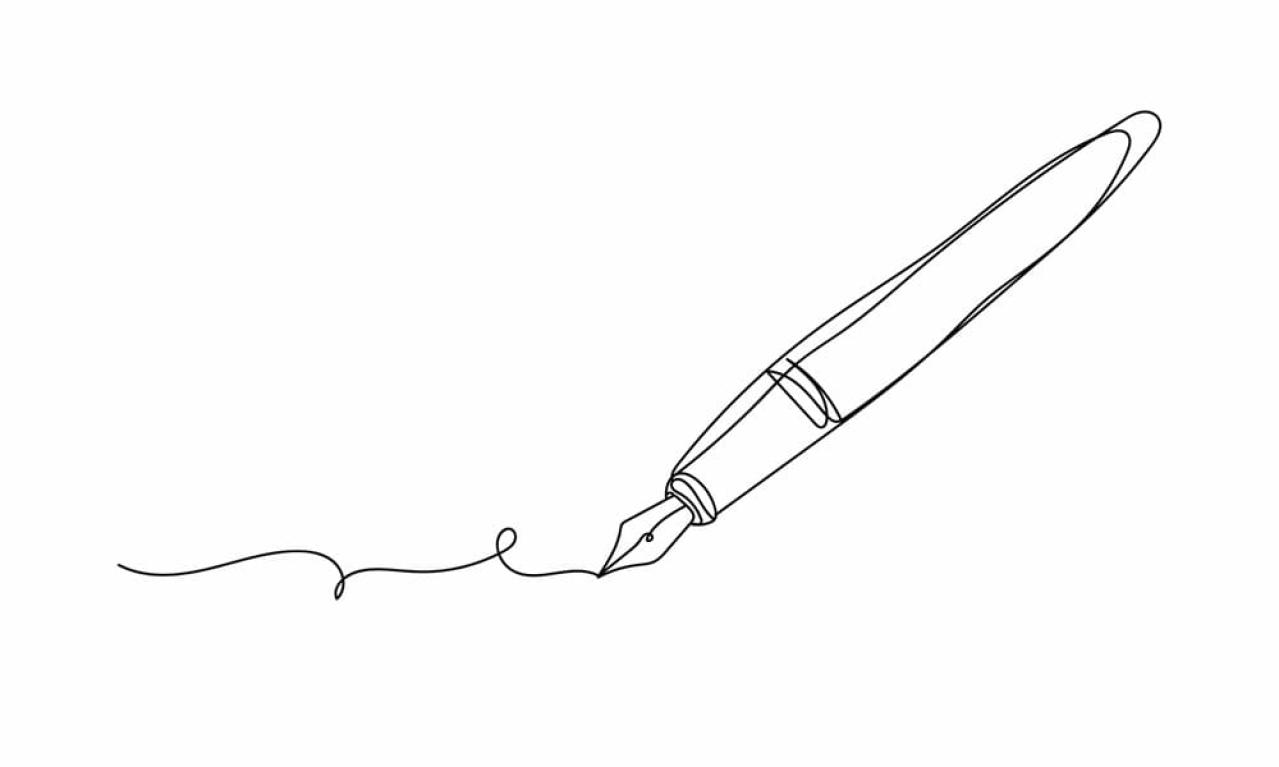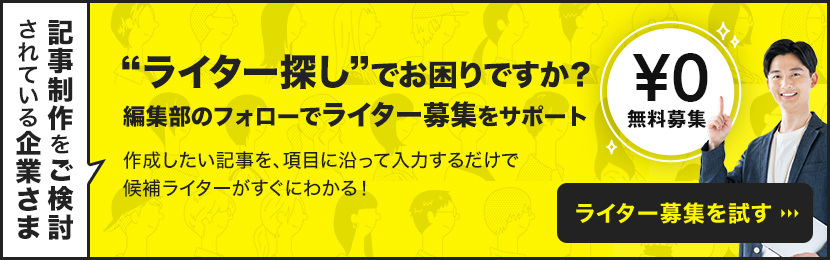「です・ます調」と「だ・である調」の違いとは?

ライティングを始めたばかりの人が最初に直面するのが「です・ます調」と「だ・である調」のどちらで書くかという問題です。
私はレギュレーションで文体が指定されている案件に出会うまでは、何も考えずに書きやすい文体で書いていました。
実際、メディア記事の執筆を依頼されたときに、自分の使い慣れている「だ・である調」で書いたことがあります。その結果親近感のない文章ができあがり、注意を受けてしまいました。
文体をしっかり理解して使い分け、より質の高い文章を書くよう心がけましょう。
「です・ます調」の定義と特徴
「です・ます調」は敬体とも呼ばれ、文末に「です」「ます」「でしょう」などの丁寧な表現を使う文体です。
例:
「この記事は文体について解説しています。」
「効果的な文章を書くためには、適切な文体選びが重要です。」
「です・ます調」は敬意を示す言葉づかいであり、話し言葉に近い印象を与えます。そのため読者に親しみやすく、直接語りかけるような雰囲気を作り出せるのが特徴です。
例えば通信系事業の紹介記事のような、難しい内容を簡単にわかりやすく伝え、紹介する場面では、「です・ます調」の特徴を効果的に活かせるでしょう。
文体の選択は、単なる語尾の違いだけでなく、読者に与える印象を大きく左右します。
「です・ます調」が読者に与える印象は、以下のとおりです。
- 親しみやすく、柔らかい印象
- 読者に直接語りかけるような親近感
- 丁寧で誠実な印象
- 初心者にも理解しやすい
- 商品やサービスの説明に適した信頼感
私は今、記事を執筆する際は、基本的に「です・ます調」で執筆しています。レギュレーションで「です・ます調」が指定されている案件も多くありました。
「です・ます調」で読みやすい文章を書けるようになれば、ライターとして高く評価される可能性が高まるでしょう。
「だ・である調」の定義と特徴
「だ・である調」は常体とも呼ばれ、文末に「だ」「である」「だろう」などの表現を使う文体です。
例:
「この記事は文体について解説している。」
「効果的な文章を書くためには、適切な文体選びが重要だ。」
「だ・である調」は、読者に客観的で簡潔な印象を与え、書き言葉としての格式を感じさせます。「だ・である調」が読者に与える印象は、以下のとおりです。
- 客観的で冷静な印象
- 知的で論理的な雰囲気
- 簡潔でスマートな印象
- 専門的な内容に適した説得力
- 事実を伝える報道的なニュアンス
また、一文が「です・ます調」より短くなる傾向があるため、情報量の多い文章でも読みやすくなる場合があります。
例えば私が歴史系の記事を執筆した際には、情報を詰め込む必要があり「だ・である調」を使用しました。
ほかにも商品を紹介するキャッチフレーズやLPを執筆する際にも「だ・である調」を使ったことがあります。
「です・ます調」が適している場面3選

ここからは、「です・ます調」が適している場面を3種類紹介します。
1. 初心者向けの解説記事
専門知識に不安がある読者に対しては、親しみやすい「です・ます調」が心理的ハードルを下げ、内容に集中してもらいやすくなります。
IT技術の初心者向け記事では「です・ます調」を使いました。初心者へ専門用語や難しい概念に抵抗感を与えないためにも「です・ます調」を使うことが効果的です。
2. 商品・サービスの紹介記事
「です・ます調」は読者に直接語りかける形になるため、商品の魅力や特徴を伝える際に親近感と信頼感を与えられます。
商品を購入する際やサービスを利用する際には、読者は安心感を求めているものです。アプリ紹介記事を執筆した際には、「です・ます調」を使い、プロフェッショナルな印象と同時に、読者に寄り添う姿勢を表現しました。
3. ハウツー記事
手順や方法を説明する記事では「○○してください」「△△しましょう」といった指示が自然に入るため「です・ます調」が適しています。
手順を丁寧に案内することで、読者は記事の内容に信頼感を持ちやすくなります。実際に、格安SIMの紹介記事を書いた際には、複雑な手順をできるだけ丁寧に、読者に寄り添う形で伝えるために「です・ます調」で執筆しました。
「だ・である調」が適している場面3選
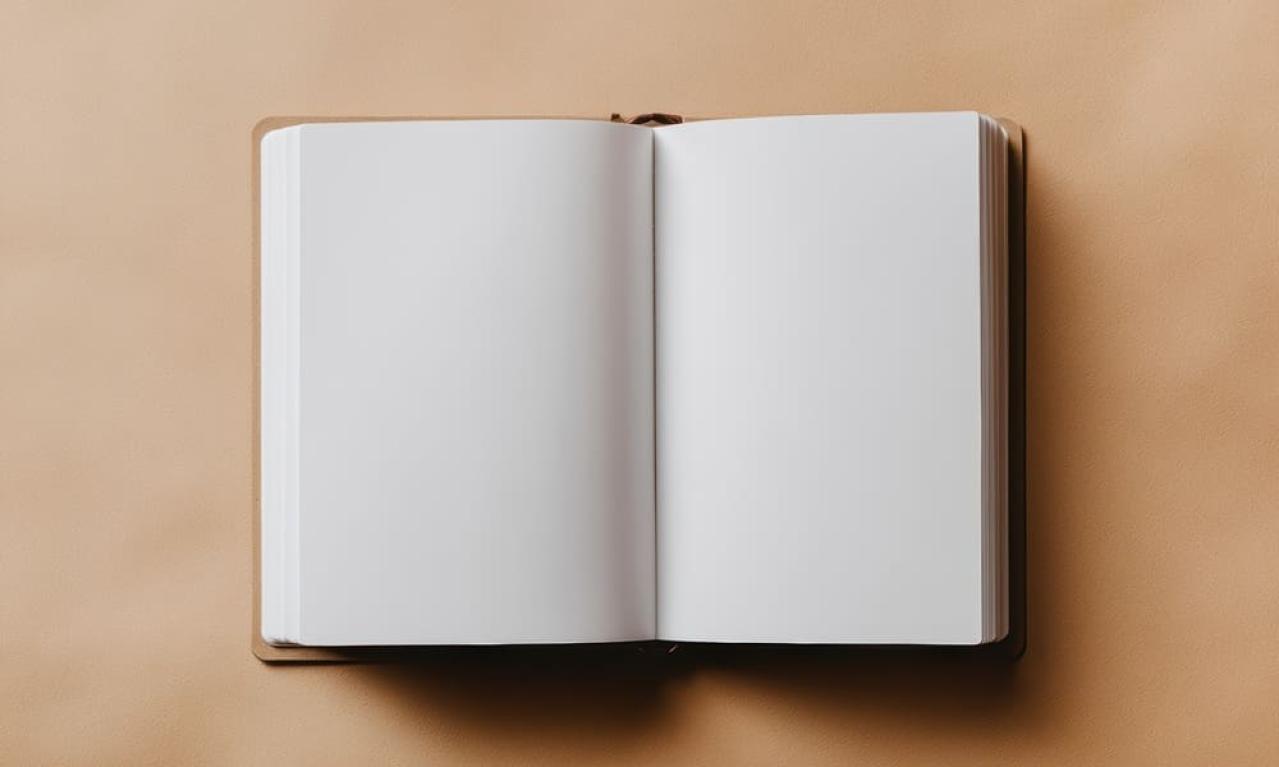
ここからは、「だ・である調」が適している場面を3種類紹介します。
1. 専門的な情報を提供する記事
学術的な内容や専門家向けの記事では、客観性と簡潔さを重視する「だ・である調」が説得力を高めます。
読み手が専門家であれば、過度に丁寧な表現よりも要点を簡潔に伝える文体が好まれる傾向があります。学術的な情報は、客観的事実として表現した方がいいため「だ・である調」が適しています。
歴史系の記事を執筆した際には、「だ・である調」を使用しました。
2. ニュース記事や報道系コンテンツ
事実を客観的に伝えるニュース記事では、「だ・である調」が適しています。かっちりした文体によって、主観を排除した中立的な印象を与えられます。
報道の基本は事実の正確な伝達であり、記者の個人的な感情や意見を含まないことが重要です。「だ・である調」により、情報の信頼性と客観性が強調され、読者に公平な判断材料を提供できます。
3. 論説や評論記事
自分の意見や主張を論理的に展開する場合「だ・である調」の方が論理の流れを強調できます。
論理展開では「だ・である調」により無駄な装飾を省き、主張と根拠の関係性をわかりやすく表現できます。特に反論を想定した議論を展開する場合、簡潔で力強い文体が読者の理解を助け、論点を明確に伝えられます。
「です・ます調」と「だ・である調」を使うときの注意点

「です・ます調」と「だ・である調」は、ライティングにおいて「読みやすさ」や「伝わりやすさ」に大きく影響を与えます。
文体を使い分けることには、いろんなメリットがあることを紹介してきました。しかし、「です・ます調」と「だ・である調」を使う際には注意点もあります。
文体は一つの記事内で統一する
「です・ます調」と「だ・である調」を使う際に、最も重要なのは文体の統一です。「です・ます調」と「だ・である調」が混在すると、読者に違和感を与え、読みづらい文章だと判断されてしまいます。
ただし、本文は「です・ます調」で書かれている記事の見出しが「だ・である調」であるケースは珍しくないようです。そういった案件の経験は、私にもあります。
いずれにせよ、記事全体に統一感を持たせることが大切です。
繰り返し同じ文末表現を使わない
文体の統一を意識しながら文章を書いていると「〇〇です。〇〇です。〇〇です。」のように同じ文末表現を繰り返してしまうことがあります。
同じ文末を繰り返してしまうと、文章が単調になってしまいます。読みづらくなるだけでなく、多くの案件では禁止事項にも含まれているため、注意が必要です。
私は、同じ文末表現を繰り返さないように、文章が完成した後に、読み返して文末チェックをしています。
「です・ます調」と「だ・である調」の文末表現一覧

文章の質を上げるためにも、文末表現のバリエーションを増やすことが重要です。同じ文末表現の繰り返しも防ぐことができ、文末に悩まされる必要がなくなります。
「です・ます調」の文末表現バリエーション
- です(断定):「この方法が効果的です」
- ます(動作):「次の手順に進みます」
- でしょう(推量):「多くの人が悩んでいるでしょう」
- ください(依頼):「この点に注意してください」
- ましょう(勧誘):「一緒に考えてみましょう」
- ですね(同意):「重要なポイントですね」
- でした(過去):「効果があった方法でした」
- ですか(疑問):「どのような印象を受けますか」
「だ・である調」の文末表現バリエーション
- だ/である(断定):「この方法が効果的だ/である」
- する(動作):「次の手順に進む」
- だろう/であろう(推量):「多くの人が悩んでいるだろう」
- だった/であった(過去):「効果的な方法だった」
- か(疑問):「どのような印象を受けるか」
- のだ/のである(説明):「そのために必要なのだ」
- といえる(断定):「効果的な方法といえる
- ない(否定):「効果が期待できない」
私は、駆け出しの頃に同じ文末表現を繰り返さないことを意識していたので、文末表現を調べながら執筆していました。
「です・ます」の2種類の文末を交互に繰り返しているだけだったため、いろんな記事を参考にしながら、「でしょう・ですね」といった文末を使うようになりました。
まとめ:適切な文体を選んで文章の質を向上させよう
適切な文体を選択し、表現の幅を広げることで、読者に伝わりやすく、印象に残る文章を書けます。
もし文体に迷った場合は、読者がどんな人か、何を求めているかを想像してみましょう。読者目線に立って考えれば、適切な文体が見えてくるはずです。
この記事を書いたライター

まさひろ
世界一周したコピーライター。カナダ・ドイツへの留学、世界24か国を旅して辿り着いたライターの世界。ワールドワイドな人生が人の役に立ち、楽しんでもらえるように…通信系、語学系、留学・ワーホリ系など幅広く執筆中。キャッチコピー、LPなん...