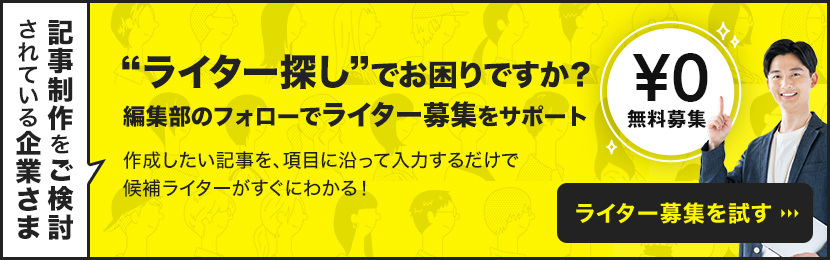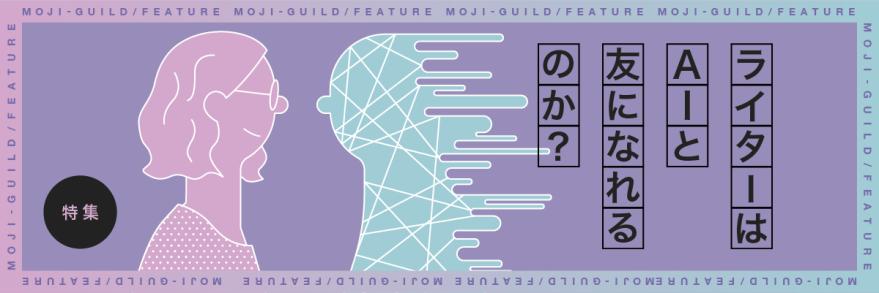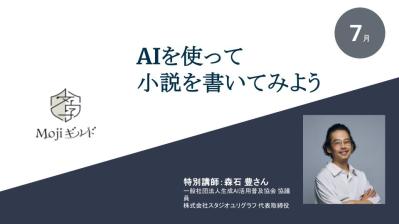AIライティングの現状|AIライティング禁止案件がある理由
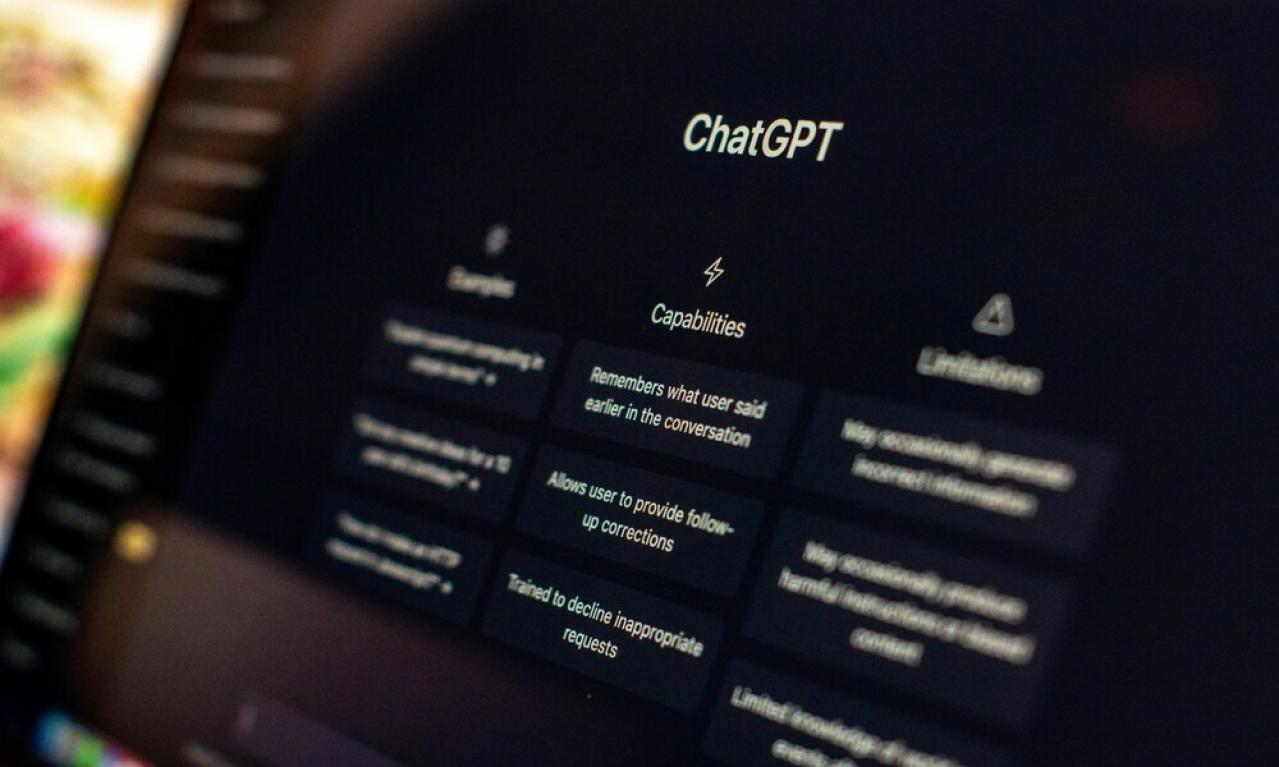
そもそも、なぜAIライティングを禁止するクライアントがいるのでしょうか?ライティングの仕事におけるAIの使用禁止案件がある背景には、以下のような理由が考えられます。
1. 品質や独自性の欠如
AIは似通った文章を生みやすく、人間らしい「揺らぎ」や創造性が不足します。
2. 情報の正確性の問題
最新情報に対応できない場合があり、誤情報を含むリスクがあります。特に医療や法律分野では記事の誤情報でメディアの信頼性を損ない、読者に深刻な誤解を与える可能性があります。
3. 著作権や盗作リスク
学習データに依存するため、既存文章に近くなる場合があります。
4. SEOへの悪影響
品質の低いAI文章は検索エンジンにスパムと判断され、評価を下げる恐れがあります。
このように、AIライティング禁止の背景には「品質確保」と「リスク回避」という明確な理由があります。筆者の印象ですが、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングでは初心者向け・低単価案件ほどAI容認であり、高単価案件ほど禁止の傾向があります。
結局のところ、ライターに求められるのは「クライアントの意向に応じて柔軟に対応する姿勢」です。
「AI判定」とは?|AI生成文か人間の文章かを見分ける仕組み
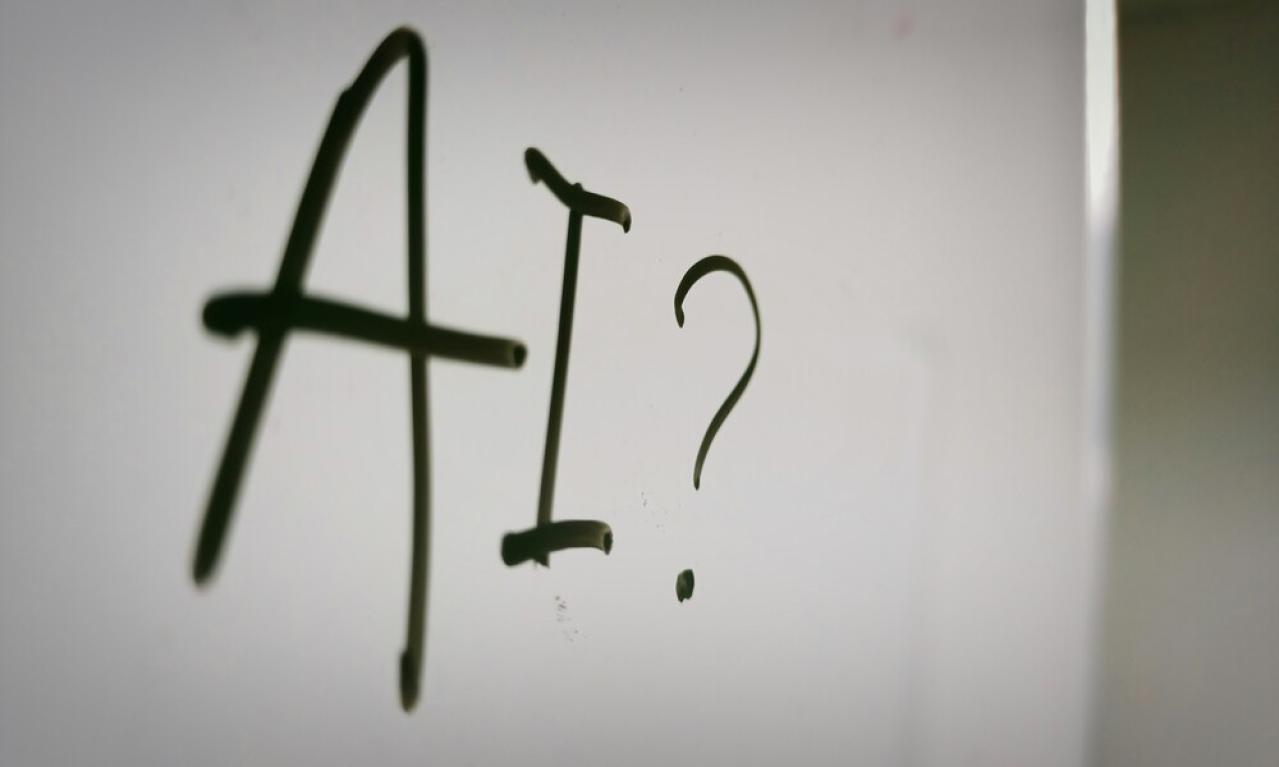
では、どのようにしてAIが書いた文章か、人間が書いた文章かを見分けているのでしょうか。 実際に人が目で確認する場合もありますが、「AIチェッカー」と呼ばれる判定ツールが活用されることがあります。
ツールにも種類がありますが、一般的には文章の構造や語彙の使い方、表現の一貫性や感情の出し方といった特徴を解析。文章の予測のしやすさ(=次に来る言葉がどれくらい想像できるか)や繰り返し表現といった、AI特有の文体パターンを見抜くことで、AI生成の可能性をパーセンテージで示す仕組みです。
しかし、この判定が万能というわけではありません。
AIが進化しているため、人間が書いた文章でもAIと誤判定されるケースも存在します。ツールによって、判定結果が違うことも珍しくありません。筆者も以前、AI禁止案件で文章を提出した際、ツールでAI判定されて焦ったことがあります。
したがって、AI判定ツールはあくまで「補助的な指標」と認識して活用するのが適切です。
AI判定ツールの種類|代表的なサービスと特徴
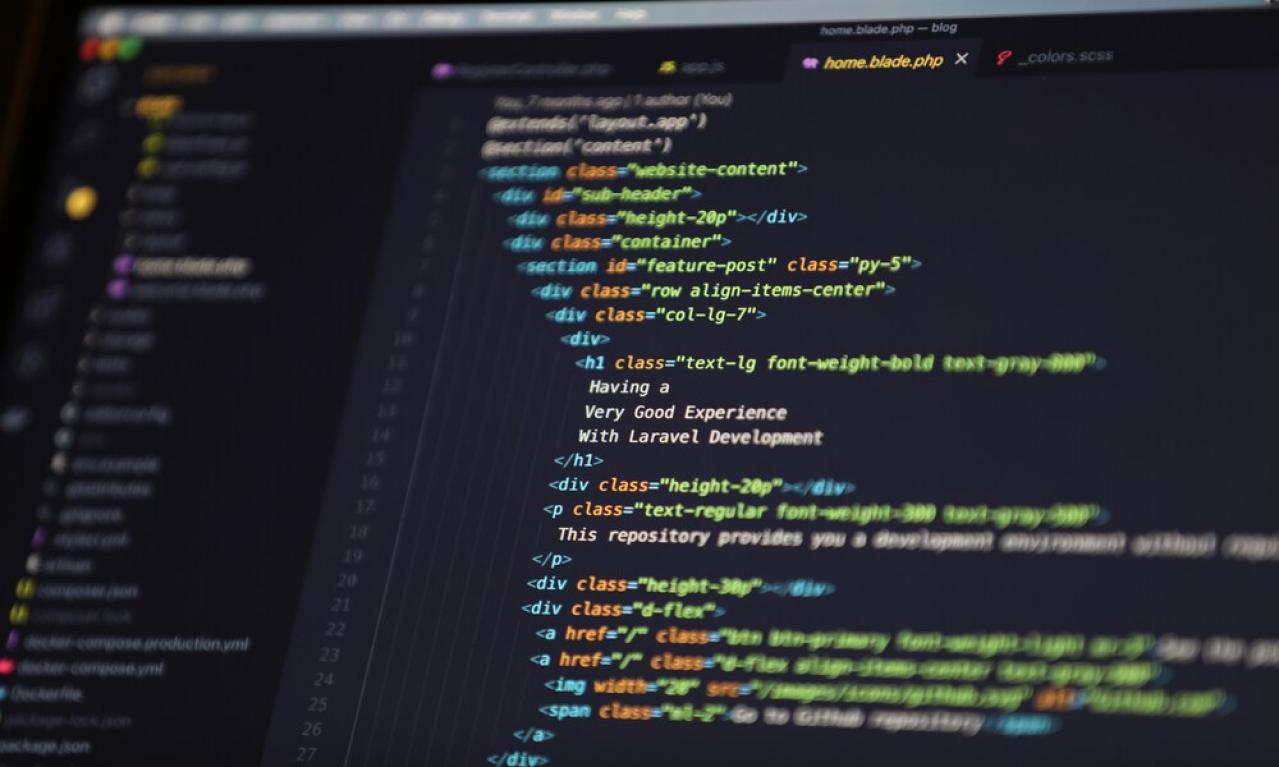
AI判定ツールにも、さまざまな種類があります。ここでは、代表的なサービスをいくつか見ていきましょう。
- GPTZero
- 生成AIチェッカー
- isgen.ai
教育現場でも広く使われるツールで、文章内のAI生成部分を一文ずつハイライト表示できます。
文章の「AIらしさ」をパーセンテージで示し、アカウント不要で最大10,000文字まで判定可能。
公式サイトでは高精度なチェックが可能とされています。様々な言語に対応しており、会員登録すると文章の解析や分析などの機能を使えます。
クライアントからAI判定を求められたときや、疑いをかけられたくないときには、これらのツールを上手に活用しましょう。ただし、オンラインで文章を送信して解析するため、機密情報や個人情報を含む文章は避けることをおすすめします。
AI判定されやすい文章の特徴|機械的だと思われるポイント

AI判定ツールを用いた場合、人間が書いた文章でもAI判定されることがあります。
では、具体的にどのような文章が「AI生成の文章」と見なされやすいのでしょうか。傾向として指摘されている主な特徴は以下の通りです。
・独自性や創造性の欠如
情報の羅列や定型的表現に偏る文章はAI判定されやすいとされます。
・不自然に流暢な文法
完璧すぎる文法や一定のリズムは、人間らしい揺らぎがなく、かえってAI判定されやすい傾向があります。
・同じ論理展開や定型文の繰り返し
「まず〜、次に〜」といった画一的な構成や決まり文句はAIっぽさを強めるとされます。
・冗長な表現
一文が長すぎたり、同じ意味の言葉を繰り返したりする文章もAI判定に引っかかりやすいとされます。
・感情表現が乏しい
体験談や独自の考察が少ない文章は、AI判定されやすい傾向があります。
・文構造が均一でリズムがない
文の長さや構造が一定な文章は、AI判定されやすい傾向があります。
・単語や表現の単調さ
特定の言い回しや単語を繰り返している場合、AI特有のパターンとして判定されやすくなるとされます。
これらのポイントを意識するだけでも、AI判定に引っかかりにくく、自然で人間らしい文章作りに役立ちます。AI判定に引っかからないように、または引っかかった際の手直しの際は、これらを意識してみてください。
AI判定されない具体的な方法

AI判定を気にせずに文章を書くには、単に情報を並べるだけでは不十分です。
筆者の経験や感覚を交えながら、文章に独自性や人間らしさを加え、可能な限りAI判定でひっかかる可能性を下げる具体的な方法をご紹介します。
体験談やストーリー性を加える
文章に体験談やストーリー性を加えると、AI判定されにくくなる可能性があります。AIは人間のように実体験や感情を持たないため、個人的な経験や考察を盛り込むことで文章の独自性が増し、判定結果に影響することがあります。
例えば、「停電のときカセットコンロがなくて料理に困った」といったことを、
「真冬の夜に停電が起きて、冷蔵庫の中の食材をそのまま食べるしかなく、子どもに温かい食事を用意できなかったことが本当に困った」
といった具体的なエピソードにしたり、レビューや感想を参考にした創作体験を加えたりするのも有効です。
こうした工夫を取り入れることで、文章はより人間らしく、読者に共感されやすい内容に仕上がります。
口語表現を使う
文章に口語表現を取り入れると、AI判定を避けやすくなる場合があります。AIが生成する文章は文語的で整いすぎていることが多く、単一のリズムや定型文感が目立つためです。
例えば、パソコンのトラブルを紹介する記事で「なんでパソコンが動かないんだろう?」のような口語表現を加えるだけでも、文章に親しみやすさと独自性が生まれます。
しかし、案件によっては口語表現が禁止されることもあるため、使用の際は確認が必要です。上手に使えば、読者に寄り添う自然な文章に仕上がり、AI文章との差別化にもつながります。
感情表現・オノマトペを加える
文章に感情表現やオノマトペを加えると、人間らしさが増し、AIとの差別化につながる可能性があります。AIは感情を理解して文章に反映することが難しいためです。
例えば、「驚いた!」や「ワクワクする」といった筆者の感情表現の追加。「ピカッと光る」「ぐうぐうお腹が鳴る」といったオノマトペの使用が効果的です。文章に親しみや臨場感が生まれ、AIとの差別化につながるでしょう。
注意点としては、やりすぎると冗長になりかねないので、適度に使うことがポイントです。
固有名詞や具体的な数字を活用する
文章に固有名詞や具体的な数字を盛り込むと、説得力や信頼性が増し、AI判定の可能性を下げることがあります。AIは抽象的・一般的な表現になりやすいため、具体例を加えることが有効です。
例えば、「〇〇社の調査で△△を導入したユーザーの40%が効果を実感」といった具合に具体的に示すと、説得力や信頼性が増します。さらに、引用も使用すれば、説得力や信頼性も向上。日付や地名、人物名を入れることで、読者が情景をイメージしやすくなる効果も期待できます。
このように、具体性のある記述は人間らしい要素とされ、AIと判定されるリスクの軽減に役立つ可能性があります。
文のリズムを変える
文章のリズムに変化をつけると、人間らしい印象が強まり、AI判定に影響することがあります
AIはどうしても「です・ます」の連続や、一定の文の長さになりがちで、単調で機械的な印象になりやすいためです。短い文と長い文を交互に配置したり、倒置法や体言止めなどを駆使したりすることで、人間らしい文章となるでしょう。
また筆者の印象ですが、AIは話しの流れを変えるのが苦手です。例えば「なぜこれほどまでに人気となったのでしょうか」のように、文の途中で視点や話題を切り替えたり、問いかけを交えたりする文章です。
話の流れも意識することで、読者は飽きずに読み進められ、文章に自然な流れと人間らしい「揺らぎ」が加わります。結果として、AI判定を避けつつ、読者の記憶に残る文章が作れるのです。
ライターが意識すべきこと|AI時代に必要な差別化の考え方
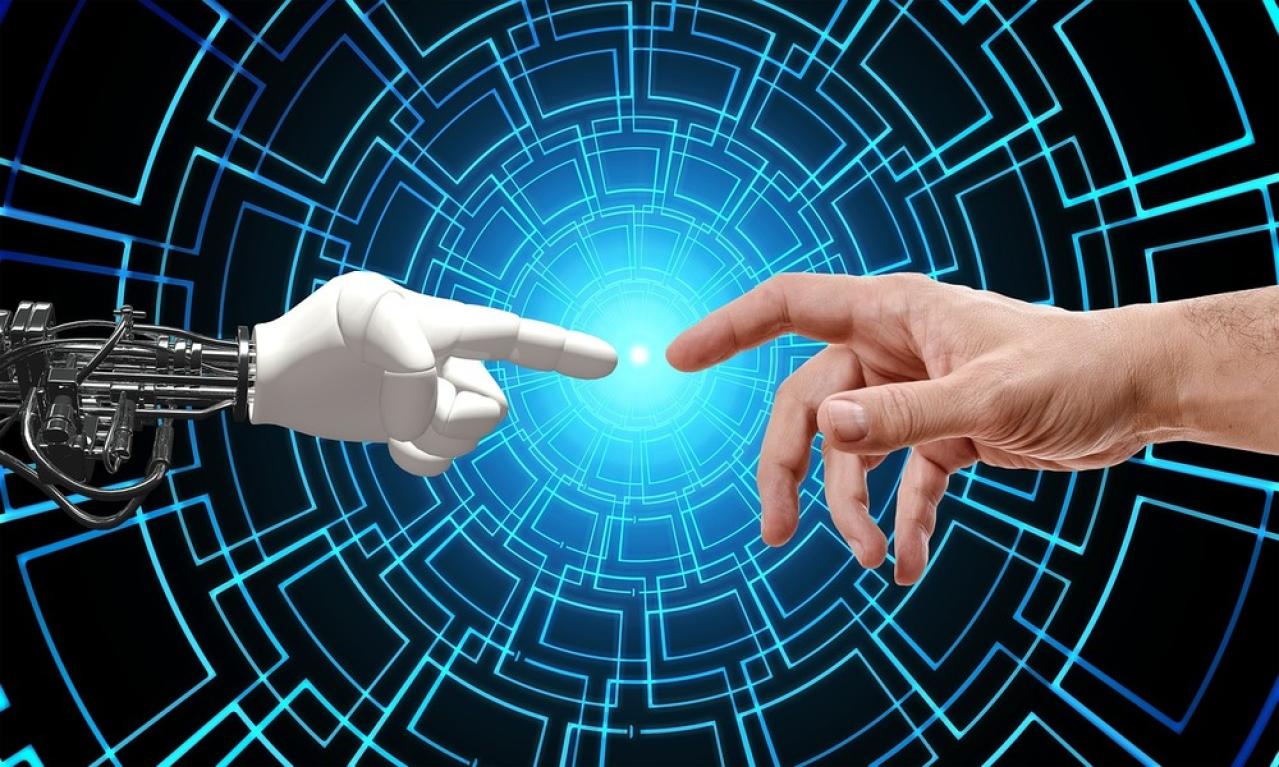
AIライティングは、Webライターだけでなく、あらゆる物書きに大きな影響を与えつつあります。これからの時代、ライターが単に文章を作るだけでは差別化は難しく、AIとどう向き合うかが重要です。
対抗するためには、AIを「答えを出す機械」として扱うのではなく、思考を深めることや拡張するパートナーとして活用することがカギでしょう。情報収集や下書き作成をAIに任せつつ、独自の視点や体験談を加えて編集することで、読者に響く文章を生み出せます。
上手く共存することで、AIの効率性と人間の感性を組み合わせ、読者の心に残る高品質なコンテンツが作れるでしょう。AI時代を生き抜くには、こうした「新しい知識と感性の形」を意識することが必要です。それが、ライターの差別化につながるのではないでしょうか。
まとめ|AI判定を理解して安心してライティングを続けるために
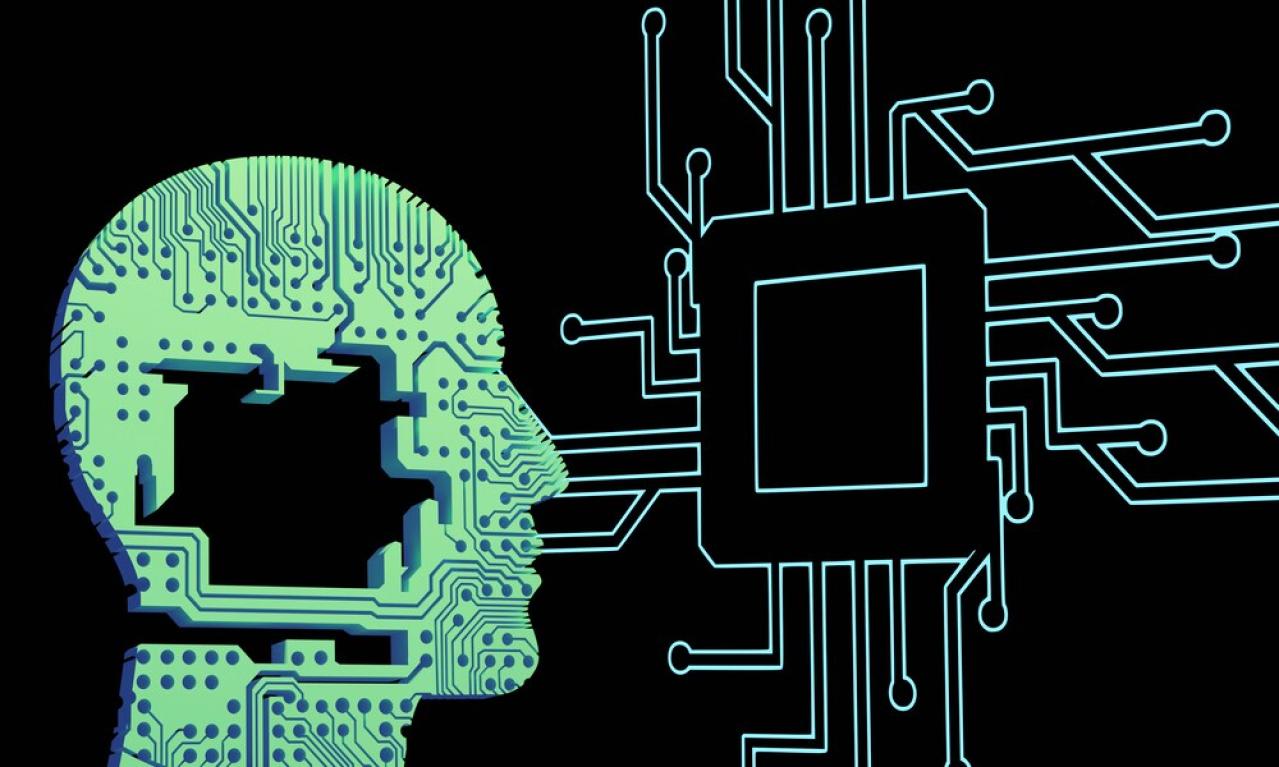
ここまで、AI判定の仕組みやAIに判定されやすい文章の特徴、そして具体的な回避方法について紹介してきました。
まとめると、AI判定ツールの精度は完璧ではなく、人間が書いた文章でも誤判定されることがあります。対策として、独自性や体験談、感情表現などを加えることが有効です。人間らしい文章を意識することで、判定を可能な限り回避しつつ、読者に価値あるコンテンツを届けられます。
最も大切なのは、AIはあくまで補助ツールであり、最終判断は「読者にとって価値があるかどうか」です。まずは自分の経験や知識を整理し、AIの出力を参考にしながら文章に磨きをかけてみましょう。こうして書いた文章は、読者の共感を呼び、記憶に残るコンテンツになります。
ちなみにこの記事も、AIに情報整理を頼りつつ、筆者の意見や体験を加えて作成しています。AIは味付けの補助、最後に味を決めるのはやはり人間のライターなのです。
この記事を書いたライター
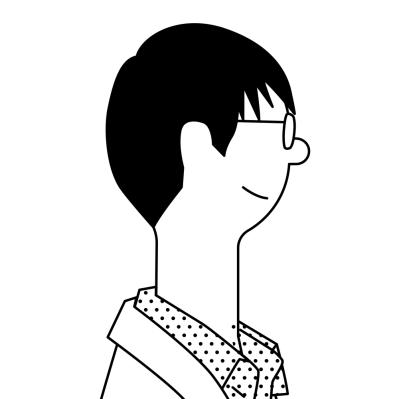
水木ゆう
フリーランスのWebライターです。自身でネットショップを運営していた際に、ブログを執筆したことでライティングに興味を持ちました。得意なジャンルは「歴史」「アニメ」「ゲーム」「観光」などです。また、ナレーターの勉強をしていた経験があ...