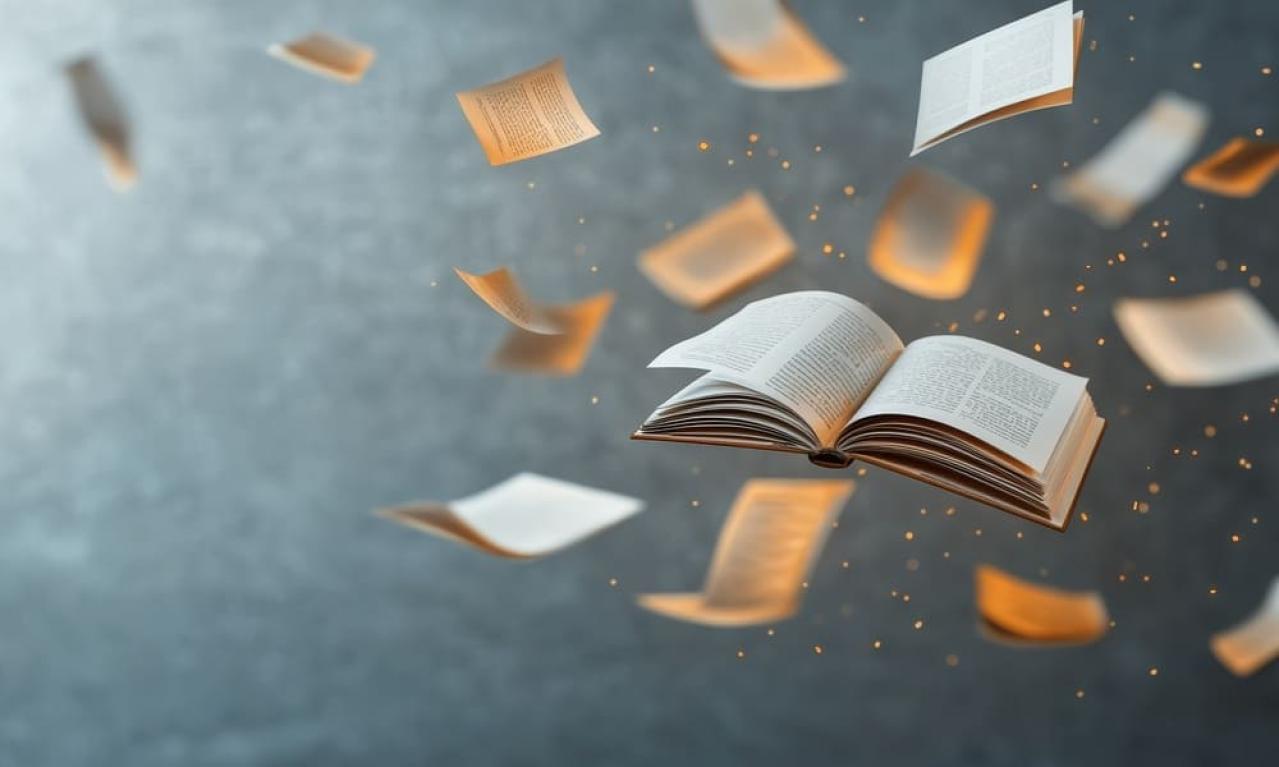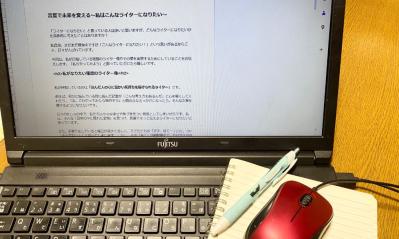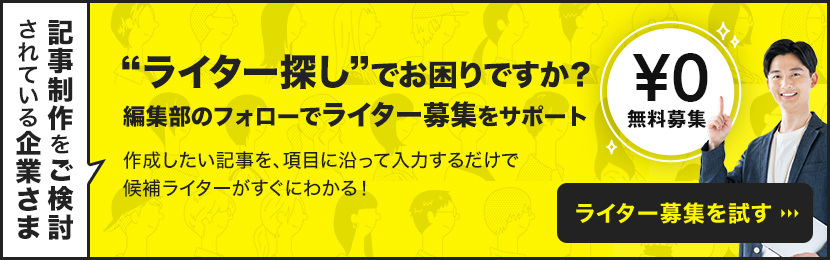文章にリズムをつける7つのコツ

文章のリズムをよくするには、次の7つのコツを意識してみましょう。それぞれ詳しく解説していきます。
①文の長短を意識する
短い文と長い文を組み合わせることで、読者が一呼吸置けるようになります。
私の場合、文の長短を意識することなく、ひたすら長い文章を書いてしまうクセがありました。無意識に読者を「息継ぎができない」状態にしていたのです。
しかし、厄介なことに文章を書いているときはなかなか気づかないものですが「一度読むだけで、意味が伝わる文章」を意識するようにしました。
×読みにくい例
「私は昨日、友達とカフェに行って珈琲を飲んで、そのあとショッピングを楽しみました。」
〇読みやすい例
「昨日は友達とカフェへ。コーヒーを飲んだあと、ショッピングも楽しみました。」
適度に文を区切ったことでリズムが生まれ、読者からも「読みやすい」と言われることが増えました!
②接続詞を上手に使う
接続詞を減らすことで、文章がスムーズな流れになります。
「そして」「しかし」などの接続詞はとても便利ですが、多用すると文章がくどくなります。私も以前は接続詞を多用してしまい、読みづらい文章になっていました。
文章のリズムを意識するようになった結果、接続詞を削ったり、言い換えたりすることで文章がスッキリし、より自然な流れになると気づきました。
×読みにくい例
「私はアメリカに留学しました。最初は不安でした。しかし、現地の人はとても優しくて親切でした。そのおかげで、すぐに馴染むことができました。」
〇読みやすい例
「私はアメリカに留学しました。最初は不安でしたが、現地の人がとても優しく親切だったおかげですぐに馴染めました。」
読みやすい文章は文章をスッキリさせること!
「その接続詞は、本当に必要なの?」「なくても意味は伝わるのでは?」と考えることでリズムの良い文章が作れます。
③句読点の使い方を工夫する
読点を減らし、短めの文に区切るとリズムが良くなります。
読者は一文が長いと、ストレスを感じてしまいます。一般的に一文は30文字〜50文字以内が読みやすいとされてます。
読みやすい一文を作るには、句読点を上手く使いましょう。
×読みにくい例
「お昼ご飯を食べて、お腹がいっぱいになり、午後は眠くなりました。」
〇読みやすい例
「お昼ご飯を食べてお腹いっぱいに。午後は眠くなりました。」
私も以前は句読点を適当に入れてしまい、読みづらい文章になっていました。しかし、句読点を適切な位置で区切るだけで、グッと読みやすくなります。
④ひらがな・カタカナ・漢字のバランスを意識する
執筆するときは、ひらがな・カタカナ・漢字のバランスを意識しましょう。
私は漢字を多用しすぎてしまい、クライアントにしまい、クライアントに「堅苦しい」と言われたことがありました。柔らかい印象を持たせるためには、必要以上に難しい漢字を使わないことがポイントです。
×読みにくい例
「昨日映画を観たが、内容が難解難解で理解し辛かった。」
〇読みやすい例
「昨日映画を観たけれれど、内容が難しくてよくわからなかった。」
漢字を減らしたことで表現が柔らかくなり、グッと読みやすくなります。
⑤開く漢字と閉じる漢字を使い分ける
漢字には「開く」と「閉じる」という使い分けがあります。
「開く」は、難しい漢字をひらがなにして、文章を柔らかくすること。「閉じる」は、漢字を使って意味を引き締め、文章をわかりやすくすることです。
例えば「出来る」「事」「為る」などは、漢字で書くと少し堅苦しい印象を与えます。これらを「できる」「こと」「する」と開く(ひらがなで表記する)ことで、文章が柔らかくなり、読みやすくなります。
開く前:「この事を理解出来る人は少ない。」
開いた後:「このことを理解できる人は少ない。」
私は開き言葉と閉じ言葉の使い分けは、Webライターを始めてから知りました。
それまでは文章を読んでも「開く」漢字と「閉じる」漢字を意識したことがなかったため、最初の頃は「この漢字は開いた方がいいのかな?」「それとも閉じるべき?」と迷うことも多く、開けるもの全てを漢字にしてしまっていました。
しかし、Webライターとして仕事をするようになってから、開く漢字と閉じる漢字の使い分けができるようになりました。
漢字を適度に開くことでリズムが生まれ、スラスラと読めるようになります。
⑥改行や段落を工夫する
文章が詰まりすぎていると、読者は「読むのが大変」と感じ、離脱してしまう原因にもなります。
×読みにくい例
「今日は忙しかった。まず、メールをチェックして、そのあと会議に参加して、そのあとまた資料を作成して……。」
〇読みやすい例
「今日は朝から忙しかった。
まずは出社してすぐにメールをチェックし、会議へ参加そのあと資料を作成ををしていたら、気づけばあっという間に夕方だった。」
現代はスマホで記事を読む人も多いので、画面いっぱいに文字が詰まっていると、それだけで「読みたくない」と先入観が入り、読者にストレスを与えてしまいます。
その解消法が改行や段落の調整です。
私は個人でブログを運営していますが、改行を意識していなかった頃の記事を読み返すと、ぎっちりと文章が詰まっていました。一瞬で「読みづらいな」と感じます。
クライアントからフィードバックをもらう中で「もっと文字の間隔をあけた方がいいよ」と言われることもありました。「そんなにあけるの?」と思ったこともあります。
しかし、普段自分が目にしている文章は、改行やいくつもの段落に分けられていることに書く側になって初めて気づきました。
改行や段落も、ぜひ意識してみてください。
⑦音読してみる
実は、私が一番効果を感じたのは「音読」です。私が一番効果を感じたのは「音読」です。
書いた文章を声に出してみると、リズムの悪い部分がすぐに分かります。
最初は「音読することが面倒だな」と感じることもありました。
しかし、音読を習慣にしてからは「あ、ちょっとここ読みにくい」と気づく回数が増えたため、原稿を修正するスピードも上がりました。
×音読修正前
「私は昨日友達とカフェに行き、そこでコーヒーを飲んでからショッピングを楽しみました。」
〇音読修正後
「昨日は友達とカフェへ。コーヒーを飲んだあと、ショッピングも楽しみました。」
自分の書いた文章を、声に出して読んでみましょう!
文章のリズムを整える7つのコツで、読者に優しい文章を書こう!
今回紹介した7つのコツを意識するだけで、文章のリズムがよくなり、読者にとってストレスのない読みやすい文章が作れます。
- 文の長短を意識する
- 接続詞を上手に使う
- 句読点の使い方を工夫する
- ひらがな・カタカナ・漢字のバランスを意識する
- 開く漢字と閉じる漢字を使い分ける
- 改行や段落を工夫する
- 音読してみる
私自身が実践して大きく改善できた方法なので、ぜひ試してみてください!
スラスラと読めて、心地いい文章を作成していきましょう!
この記事を書いたライター
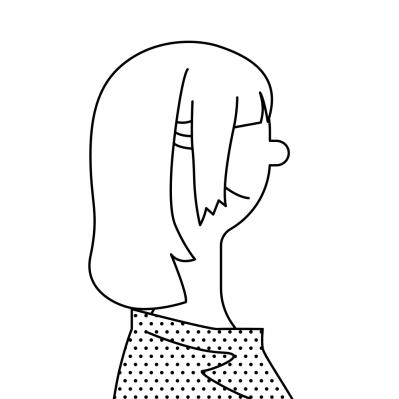
増田なな
元気な2人の男児を育てるママライター。デイサービスと病院で働いていた介護福祉士。自己表現が苦手な自分が「誰かの助けになりたい」という思いでライターへ。医療系の記事を多めに書いています。自身でブログも運営中。バスケは8年間経験があ...